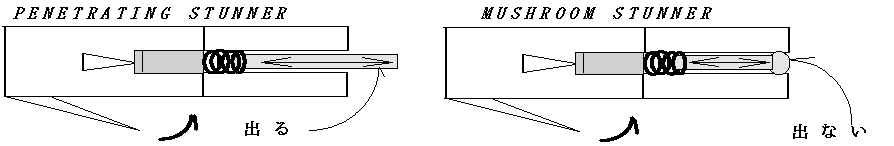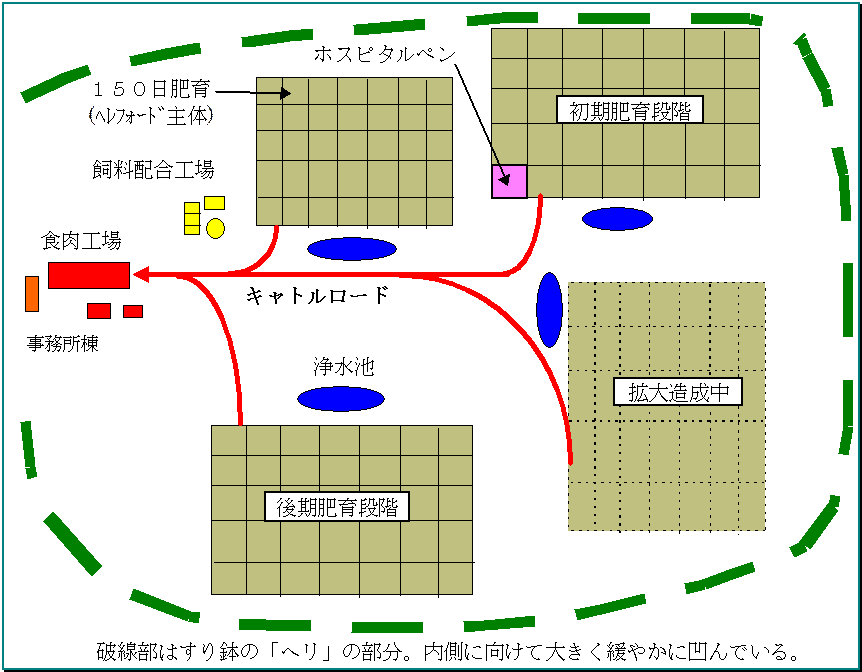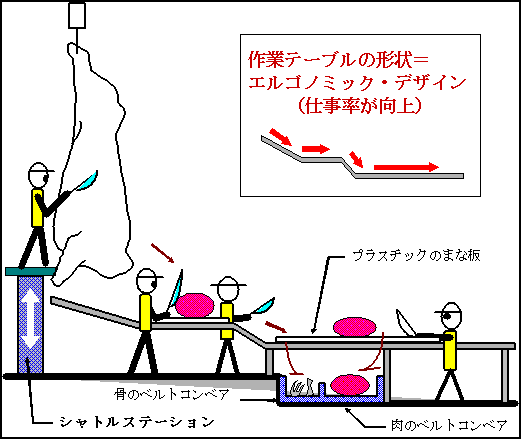|
オーストラリアのビーフ業界では、1990年代の前半に様々な技術が導入され、実験されました。 これらの技術は情報を公開し、広く意見や経験を集め、いかにもオーストラリアらしいフェアな精神に裏打ちされていました。 こんご日本にも多くの点で参考になると考え、ここに再録しました。 1.
FUTUTECH-「自動と畜システム」の壮大な夢と挫折
フューチャーテックとはMRCの主導の下CSIRO、BHPなどの協力で研究・開発された壮大な「全自動と畜技術開発計画」のことで、1978年の構想以来じつに15年の歳月と30百万豪ドルを費やしました。1993年からはキルコイ社の協力で同社に導入され、1994年5月より商業化の予定でした。しかし、1994年9月1日資金的・技術的な問題をどうしても解決できず残念ながら中止となりました。 これが実現するとlabour cost 30%のセーブ、作業中の被傷率の大幅な減少が期待できるとされ、生体重220ー800kgの牛のと畜が可能で能力は約100頭/時間となっていました。システムの概要としては、以下の模式図のように、水圧式を主体とする各モジュールと、各々のモジュールを自己制御するコンピューター及び全体のモジュールを統御するマスター・コンピューター・システムから成っていました。その特徴は全自動であることの他、牛のと体を仰臥位で固定・処理することでした。 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 計画は中断することになったものの、この試みは注目に十分値すると思われるので以下に詳細を紹介しましょう。 a)
歴史
(1) 構想:1978年
(2) 実験:1988〜1991年。於CANNON HILL。BHPをスポンサーとして3年間の開発。
(3) 1993年2月商業化を目指しキルコイ社にMARK Iとして導入するも、1994年8月実現の可能性がないと判断。計画は中止となった。予定では、1994年2月にフル稼動、3カ月の実験運転の後、キルコイ社に売却。1994年中頃から約12カ月の間
MARK IIとして豪州国内食肉業界に販売、その後国外にも販売の予定であった。更に1999年までには本システムを順次に発展・開発し、「MARK V」として生体から部分肉の箱詰めまでの全自動化を実現する壮大な構想があった。
(4) 開発したうちの7つのモジュール(固定、打額、脊割り、頭部除去、食道端ゴム止め、心臓刺し、リブ除去モジュール)は国内の業者に販売予定。
b)
全体の概要・特徴
(1) 開発者:Fututech Pty.Ltd.(1992年6月MRCが設立した会社)
(2) 生体導入路〜懸肉室搬入迄をほとんど自動化。生体導入〜懸肉室搬入までの処理速度:約40分で通常と同じ。
(3) 生産コストの削減:約30%
(4) 300〜800Kgsの生体重の牛を8時間で600頭処理。
(5) 手動で規格外の牛も処理可能(モスレム・キル=回教式と畜も可能)
(6) と体を仰臥位で処理
(a) 自重による余計な力がかからないので、放血は従来と変わらない。
(b)
自動化により手で触れる機会が少ないので衛生的である。
(c)
カーカス同士が触れないので複合汚染(cross contamination)が無い。
(d)
機器を一頭処理毎に自動殺菌
(7) 面積
l 通常のと場 :1,050 sq.m. (600頭) l Mark I :1,500 sq.m. (600頭) l Mark II :1,800 sq.m. (900頭) (8) 価格(MARK II):8百万豪州ドル(約6億4千万円)
4社が興味を示したが契約には至らなかった。設置には約2年必要。実質的な減価償却6〜7年。(週5日シングルシフトの場合) (9) その他
枝肉の品質の向上の研究。(柔らかさ、ペーハー、肉色、ドリップ=“WEEP”の改善) 社会的な3Kイメージからの脱却。 c)
各モジュールの概要
(1) と畜・放血モジュール
1. 同一サイズの6頭単位での導入。曲線状の生体導入路は、音の発生・明るさを抑えており、と畜前のストレスを最小にする。 2. 打額室への導入路部分は、W字状のコンベアとなっている。(生体は身動きできない。) 3. 打額室の壁は、牛のサイズにより自動的に変えられる。 4. 打額室の入口は牛が近付くと開口するようになっている。 5. 牛の首の固定機についたセンサーが、牛の頭が入ったのを確認し起動する。 6. 床が下に落ち、自動打額機が2回(4秒、0.5秒間隔で更に4秒)作動する。 7. 打額後、マジックハンドが牛の首を掴み、頚動・静脈切断場所まで移動しこれを切断する。自動角切断機が降りてきて角のある場所を感知しこれを切除する。 8. と体は放血レール(頭部支えつき)に降ろされ、90秒放血する。 9. 血液の流出溝がコンベアの真下に設けてあり、レールには自動ベラがついており、自家清浄する。 10. 最後に2段階式起重機で、と体を放血コンベアから3つの架台を設けた幅の広い温と体仕上げコンベアに移動する。 11. 以上一連の工程が、一体のモジュール(一単位)となっており、現在業界のもっとも関心を集めているものである。 一般的な打額器(stunner)は次図のようにpenetrating stunnerと呼ばれるもので、薬莢を充填し火薬の力で金属棒を牛の額に突き入れる方式になっている。 これに対し回教徒国向けのと畜方法(halal=Moslem slaughter)に使用されるものは先が丸いmushroom
stunnerと呼ばれ、脳震盪を起こすのにとどめ、この後の頚動脈の切断を回教本来のと畜手段としたものである。 この他に火薬の代わりに圧縮空気を利用したものや、電気式のものも見られる。
(2) 開腹モジュール
1. 各々の架台での作業は手動でと体の開腹・部分剥皮・食道端のゴム止め及び内臓摘出の前作業を行う。 2. 二人一組になった3〜4組がこの回転コンベアで手作業できる。次の工程である皮剥ぎモジュールに移すまで所要時間は数分である。四肢端・乳房(タマアブラ)及び他の切除片は、このコンベアの末端に設置されたトリムコンベアに落とされる。 3. 最後に、四肢のアキレス腱にフックをかける。2本のレールに仰向けに吊す。レールは種々の作業をする為に異なった角度で枝肉が傾くように、その断面が丸くなっている。 (3) 皮剥ぎモジュール
1. 専門家によると、大きな枝肉は二本のレール間で枝肉の中間がたわむが小さな枝肉はしっかりと広がるとのこと。 2. 二つの手作業台がありここでは頭部を処理し、シュートに鼻口部とクズを落とす。 3. 剥皮は、GA、G1、G2及びG3とよばれる四つの設備からなっており、各々の機械についたセンサーが枝肉の違いを感知し機械を設定する。 4. GAは吊された枝肉の角度と高さを測定し設定する。 5. G1は例え恐竜の枝肉がその上に落ちても壊れそうにない強大な機械で、皮を左右に剥ぎ降ろすが、背の部分は帯状に枝肉につけたままとする。 6. G2はこの帯状の部分を枝肉から切り離す特別の機器を装備している。 7. G3は頭部から皮を剥ぎ取り、巻き上げシュートに落とす。G3には、枝肉に触れることがないため殺菌設備はない。 8. 担当者によるとこの剥皮機には、脂肪の角と皮筋の剥離にやや不安があるだけで他は最高の出来であるという。 (4) 寛骨切断モジュール
1. 枝肉はそのままチェーンを進み、吊す角度を傾斜させ手作業で肛門端をゴム止めした後、センサー装備した自動寛骨切断機に進む。 (5) 頭部除去モジュール
1. 次に枝肉は、反対側に傾斜を変えて自動で頭部除去される。 2. フューチャーテック開発チームは、この頭部除去モジュールを「次世代の設備」と呼んでおり、フューチャーテックのMARK IIに装備されると思われる、より円滑な設備を彷彿させるものである。 3. センサーが頭部の裏側に当てられ、頭部を取っ手が掴み、刃で頭部が切断される。 4. 頭部は別の機械で自動的にチェーンに送られるが、そこでは頭部の第一回目の洗浄と手作業による舌の切断が行われる。 5. 頭部全体の洗浄・衛生検査の後、脳・舌・頬肉が手作業で除去される。 6. 残った頭部はシュートで落とされる。 7. 現時点でCSIROは脳の自動除去システムを取り入れるべくMIRINZ(ニュージーランド食肉研究所)と協議中である。 (6) 内臓摘出モジュール
1. 胸部切開機もまた自動でセンサーで動くようになっている。大型の枝肉については3回、小型については2回の切断を行う。 2. 自動内臓摘出工程では、枝肉を頭部方向を45度の角度に傾斜させる。 3. センサーが枝肉胸部の高さを決定し、内臓摘出機が胸腔・腹腔内の内臓をかきだし、その下の皿状の内臓コンベアに無傷で落下させる。 4. 皿状の形状が選ばれたのは、スペースの活用と、異なった個体の内臓が互いに接触することによる混合汚染防止のためである。 5 .大型の四角形の皿には仕切があり、各々胃袋、可食内臓類および尾を収納するようになっている。 6. もし何か廃棄しなければならないような問題が発生した場合には、廃棄シュートに中身を落下すべく皿は傾斜するようになっている。 (7) 尾切除モジュール
1. 次に枝肉は、業界標準であるジャービス社製の四肢切断機から取り入れた、尾切除モジュールを通過する。 2. レーザー光線が尾の先を感知し、これを切断し内臓の受け皿に落とす。 (8) 背割りモジュール
1. 更に枝肉は、最後の自動モジュールである背割り機のところで頭部方向を下に30度傾斜される。 2. センサーが背骨を探り当て、背割り鋸を誘導し、これを左右に分割する。 (9) 次の工程
1. 最終的に半丸枝肉は、懸垂状態を解かれ手作業での枝肉仕上げを経て、フューチャーテックの断面の丸いレールから通常の平たいレールに架け変えられ、自動洗浄機、高圧電気刺激、懸肉室に向かう。 d)
システムの制御
(1) 建物の一角にある制御室では、従業員が作業を監視でき、問題発生を即時に的確に指摘するソフトを搭載した既成のパソコン3台が特徴的である。
(2) 故障時には、警告画面が点滅し、管理画面では各々の機械のコードナンバー及び機械の断面図が映し出される。
(3) また画面上でどのモジュールが自動または手動となっているか、どこの工程で遅れが出ているかを見ることが出来る。
(4) 加えて、制御室の従業員は16台の現場監視ビデオカメラから送られてくる重要な作業現場を見ることが出来る。
e)
その他
(1) 工場の全てが完成すれば、フューチャーテックの建物の床は色分けされる。赤は危険地域でセンサーが異常を感知した場合工場は稼働停止し、黄色は障害地域、灰色は作業地域、さらにベージュ色は見学地域となる予定である。
(2) 環境の見地からフューチャーテックでは、騒音レベルを最高85デシベル(最新のと場としては標準)と設定した他、人口光を補うため窓も設けている。(これには精神衛生の目的もある。)
2. 日本資本工場Rockdaleの概要
1993年5月、かねてより豪州国内から期待されていた伊藤ハム・三菱商事資本のロックデールRockdaleビーフ工場が完成・稼働に漕ぎ着けました。同社は3年前の1990年同敷地内に20,000頭のフィードロットを完成しており、豪州ではビーフシティーに次ぐ第2のフィードロット・食肉工場一体型の設備となりました。豪州国内では、日本資本が新たに建設するハイテク工場との前評判高く、豪州畜産業合理化への好影響を期待する声が聞かれました。 詳細については以下の概要を参照していただきますが、技術的な側面では期待通りに日本から導入されたものは意外に少なく、豪州若しくはニュージーランドで考案されたものが多いのに気が付きます。むしろ特筆すべきはその斬新な就業制にあるとみてよいでしょう。この背景として、この時期豪州国内では一種の「企業内労働組合制」の機運が生まれつつあったことと無縁ではないと考えられます。(詳細は後述別項参照) (概要:1994年12月現在) a) 組織および沿革
日本資本の伊藤ハム(90%)と三菱商事(10%)によって出資・設立された、豪州ではビーフシティーBeef Cityに続く第二のフィードロット・食肉工場一体型の施設。総工費40百万豪ドル(うち20百万豪ドルは工場建設費)。93年度売上高60百万豪ドル (1) 1989年用地を買収。
(2)
1990年1月フィードロットに第一期として2万頭の収容許可を取得。
(3)
1991年1月フィードロットの操業を開始。
(4)
1993年5月食肉工場の操業開始。
b) 立地
(1) 所在地:ニューサウスウェールズ州マレー川流域マランビジー潅漑地域のヤンコ(Regulator Road, Yanko (Leeton),NSW)
(2)
水源と飼料穀物に恵まれている。
(3)
豪州南部であるため、ブリティッシュブリード(英国種肉用牛)が比較的多い。
(4)
円形競技場状の地形で水捌けが良い。
(5)
乾燥気候で病気の発生が少ない。
c) フィードロットの概要
(1)
肥育規模
(a)
第一期許可頭数(1990年〜):二万頭
(b)
第二期許可頭数 (1994年〜):四万頭
(c)
1994年11月現在実飼養頭数:28,000頭(年間延べ頭数42,000頭=年間1.5回転)。4万頭肥育に向けフィードロット拡張中。
(2) 肥育日数
(a)
240日ロングフェッド(導入月齢約18ヶ月):90%(約25,000頭)
(b)
150日ミドルフェッド:10%(約3,000頭)
フィードロット見取り図
(3) 畜種
(a)
240日肥育用:アンガス、マレーグレーおよびこれらのF1
(b)
150日肥育用:ヘレフォード主体
(4) 飼養管理
(a)
従業員数:35名
(b)
設備(特徴点のみ)
ア
過去の他フィードロットでの大量事故死事件(日本ハムのワイアラF/Dにおける大量死に対するRSPCAー王立動物愛護協会の訴訟事件等)を踏まえ、一頭当りのフィードロット面積を広くしている。また牛の熱射病防止のため日除けを設置するとともに、12,000本の植樹を施している。 イ
キャトルロードでと場に直結。 ウ
給水用ダム:200メガリットル エ
サイロ:4,000トン(200トン X 20日) オ
飼料:蒸気圧延処理の穀物(小麦主体)。オレンジカス(周辺に柑橘類の栽培多いため) カ
HGP(成長促進ホルモン剤):不使用 キ
浄化池:4ヶ所(バクテリアコントロール) d) 食肉工場(EST.517)の概要
(1)
規模
350頭(一日当り平均。と畜/ボーニングは同数)
グレインフェッド <60%> グラスフェッド <40%> *註: グレインフェッドは100%同社フィードロットからの供給。 グラスフェッドは半径600KM以内の農家からの直接購入で、キャトルバイヤーとして社員2名と現地契約バイヤー5名が購入にあたる。と畜日前日の搬入。 (2) と畜処理工程
(a) 繋留ペン:グラス用とグレイン用あり。と畜の前日搬入し、繋留中は給水のみ。
(b)
レースへの追い込み:シャワーによる洗浄後、電動回転ドアつき追い込み装置により1群10〜15頭単位で追い込む。レースはTemple Grandinのデザインによる緩やかなS字状のカーブで高さは約2m。
(c)
打額:薬莢式スタナ−使用。(電殺方式も検討中なるもスポット発生が問題)
(d)
懸垂・放血:dry landing bed、ステンレス製放血樋
(e)
剥皮:joystick control付き剥ぎ下ろし方式。(皮は生で出荷し外部工場で塩漬け後、入札販売)
(f)
内臓摘出:ヴィセラテーブル(viscera table)はニュージランドのデザインで、内臓を一頭分毎に分けて収納・搬送可能なパン式になっている。使用後も一枚ずつ自動洗浄する方式。更にシックスカート、カシラ、タン、レバー、ハツ、テール等については1ピース毎に専用の自走フックに吊るし搬送。これは豪州でも極めて新しい方式である。
(g)
脊割り:ステンレス製シャトルステーション。大型往復鋸
(h)
カーカスチラー:4室。programmatic logistic
controller付きで約20時間で芯温10℃にする。
(i)
マーシャリングルーム(枝肉仕訳室):日本向は6/7肋骨間で、その他は10/11肋骨間で分割し等級付け・仕訳。レール8本。このほかに枝肉用冷蔵・冷凍庫2室あり。
(j)
レンダリング工場:キルフロアからローリング式通路(地面スクリュー方式)を通じ別棟の工場へ自動搬入。NZデザインのレンダリング工場ではミーボン・ブラッドミール・タローを製造。
(k)
その他
ア
用水:2〜3メガリットル/日(フィードロット用含む)。と畜用には浄化水、フィードロット用には川水を塩素処理したものを使用。 イ
ボイラー:天然ガス使用。 ウ
汚水処理:浄化処理後、上澄みを敷地内の農地に散布。沈殿物は一年に一回掻きだし同様農地に散布。 (3) ボーニングルーム
シャトルステーション(ロックデールの場合) (a)
|
|
建設順 |
所在地 |
位置 |
製品仕向け先 |
建設時期 |
|
第1号工場 |
クーミニア(Coominya) EST 194 |
ブリスベンの北西約70km |
韓国向けCCS,日本 |
1994年8月操業開始 |
|
第2号工場 |
クロンカレー(Cloncurry) |
マウントアイサの東方約100km |
米国 |
予定 |
|
第3号工場 |
チャーターズタワー(Charters Towers) |
タウンズビルの西方約100km |
同上 |
“ |
|
第4号工場 |
ゴガンゴ(Gogango) |
ロックハンプトンの西南約60km |
日本、韓国 |
“ |
|
第5号工場 |
クラーモント(Clermont) |
ロックハンプトンの西約350km |
同上 |
“ |
*
第4/5工場用に10,000頭のフィードロットの建設計画あり
c)
クーミニア1号工場の概要
(1) 工場番号:EST 194
(2) 工場設備等(全て新設)
(a) 敷地:1,000ヘクタール(工場敷地445ha=A$10m)
(b)
EC認可級処理工場
(c)
畜能力:600頭(うち100頭が韓国向け冷凍4分体枝肉の予定)
:実と畜360頭
(d) と畜は電気式(回教徒国用と畜方法−ハラル・スローターも可能)
(e)
ボーニング能力:
ア
ホットボーニング:350頭/日
イ
チルドボーニング:250頭/日
(f) 労働時間:20時間/日 X 7日/週 (10時間 X 2シフト/日、2シフト/週)→別項参照
(g)
従業員数(予定):午前シフト約60名、午後シフト約30名
(h)
懸肉室(carcass chiller):6室(side/quarter 800頭)
(i)
ブラストフリーザー:1室
(j)
製品冷凍・冷蔵庫:3,000カートン
(3) 特徴
(a) と畜技術の先進国といわれるニュージーランド方式を採用し、徹底的に人件費を抑えているため、通常は処理能力の60%といわれる損益分岐点の最低処理頭数が90頭となっている。
(b)
LPガスを燃料とした自家発電設備3基を有し、電気代をセーブ。
補遺:1994年の設立当初から同社の経営難は伝えられていたが、1995年10月米国向けカウミート相場の低迷を主因とし、Coominya工場の売却が検討されました。Robin Hart氏率いるStockyard社がこの売却に大きくかかわっている模様。
Stockyard社はフィードロットを所有する生産者系で、日本向け輸出に経験の深いパッカーであるが、自らの加工工場を持ちません。同社はOakey Abottoir(日本ハム)と数年にわたり委託と畜契約を結んで来ましたが、Oakey Abottoir側の委託受入数量に限界があるため、今回の決断に到りました。
ビーフランズ社のSir McCamleyとしては、Coominya工場を売却しても第2・第3工場案の中央クウィーンズランド州での工場新設の意志は固いとしています。
しかしその後の当該工場の消息は不明です。