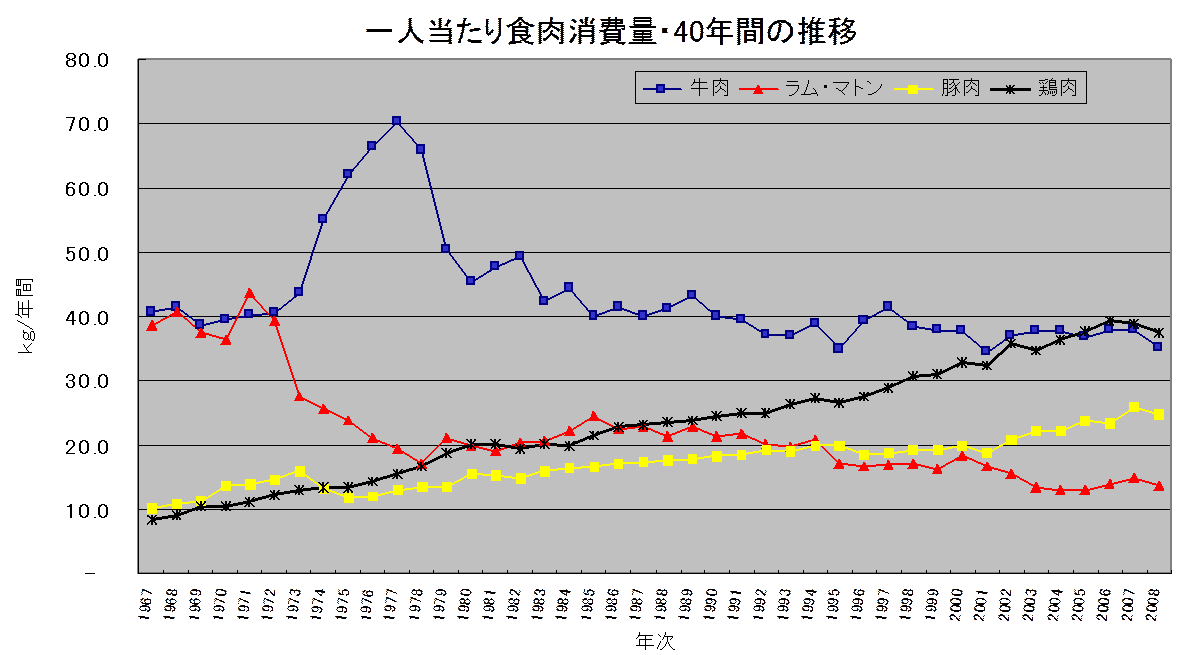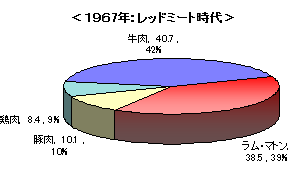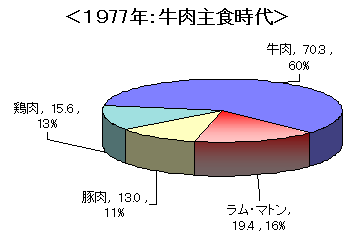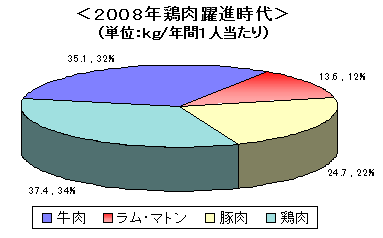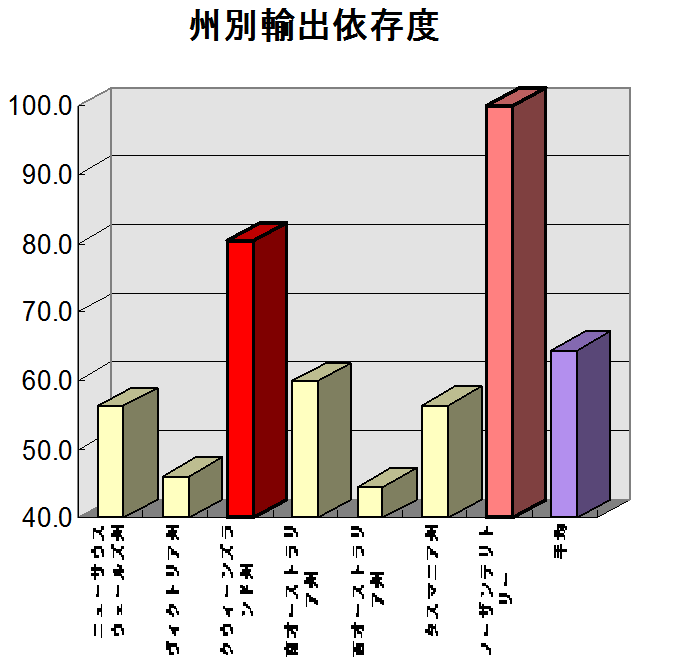A�A
����
�P. �ԓ�����Ə���X��
�I�[�X�g�����A�͋����̗A�o�ˑ��x���ɂ߂č����i���݂U�O���ȏ�j���ł��B����ł�����������P�̂̎d����ʂƌ���ƁA�����������ő�̎d������ƂȂ�܂��B ���ɐ��̂̍��ŏq�ׂ܂������A����������170�`200kgs�̎}���d�ʂ̃O���X�t�F�b�h��C�[�����O�igrass fed yearling�j�������������Y�̒��ƂȂ��Ă��܂��B �C�[�����O�͓��{�����̎}���d�ʂ�300kgs�ȏ�̃w�r�[��u���b�N�iheavy bullocks�j�A�č������̃J�E�~�[�g�icow meat�j�Ƃ͕ʕ��ŁA���������Y�`�Ԃ��قɂ��Ă��܂��B ���̓_�����E�ő�̋����̐��Y���ɂ��ď���ł�����A�����J�Ƃ̍ő�̈Ⴂ�ł��傤�B�č��ɂ����鋍���̐��Y�͊�{�I�ɂ��̖w�ǂ����������ł���A�S�̂��猩��ق�̈ꕔ�ł�����{�����Ȃǂ̗A�o�p�͍��������ƑS���������̂��A�܂��͂�����x�[�X�ɒlj���炵�����ł��邩��ł��B �܂�I�[�X�g�����A�ł́A���������Ƃ͂������������Ƒ��������̏��i���������Ⴄ�̂ł��B�����ɃI�[�X�g�����A�̋����Y�Ƃ̍\���I�E���ƓI�Ȗ��_������܂��B���������I�[�X�g�����A�ł͓��{�����̓���T�C�Y�̑傫�Ȑ����p���i���b�g�́A������������{�ȊO�̍��ւ̐U�ւ��̔�������ׁA�ǂ����Ă��P���Z�b�g�P�ʂł̐��Y�E�̔��ɂȂ炴��Ȃ��̂ł��B���̌��ʁA�I�[�X�g�����A���烍�[�X�Ȃǂ̒P�i�ŗA������͓̂����{�I�ȏƂȂ��Ă��܂��B �f�[�^�\�[�X�FABARE �f�[�^�\�[�X�FMLA a) �����E�r���������A�{���E�ؓ��͑���
���Ė{�_�̍�������ɂ��ẮA�I�C���V���b�N��1974�N����1979�N�ɂ����ĊC�O����̗A�o���v���}�������ׁA���i�͉�����1977�N�̍�����l������̏���ʂ�70kgs�ƍۗ�����������L�^���܂����B���������̌㕨�����㏸���R�X�g������ɔ��������߁A����҂̐ԓ����ꂪ�i�s���A�����̍�������͔N�X�Q�����Ă��܂��B�������i�̏㏸�ɉ����A�č����l�̏���X���\�{���̑���X���͑N���ŁA���̌X���𗠕t����悤�Ɍ{�����i�̏㏸�͂��̑��̓��ɔ�גႭ�}�����Ă��܂��B 1994�N�����̃I�[�X�g�����A�H���{�Y���Ёi�`�l�k�b�A����MLC�j�ɂ��A�C�A����L�����y�[��(iron campaign�j�́A���ɏ����ɑ���S���̕⋋��i���邱�ƂŔN�X�ቺ���鋍������ʂ��ꎞ�I�ɐH���~�߁A�I�[�X�g�����A��1995�N�̍L���܂����܂��܂����B 1996�N1���ȍ~�A�č��̋����̈���I�ȑ��Y��ƃI�[�X�g�����A�h�����ɂ��A�������i�͋ߔN�ɂȂ��\���������܂����B����ɑ������ɂ́A�����̉��i�e�͐��ɂ�����ʂ̑啝�ȉ����҂��鐺������܂��B�����������̏����������Ă��A�z���C�g�~�[�g�ւ̈ڍs���h��ς��A�ĂтS�Okg�̑��ɂ̂��邱�Ƃ͕s�\�Ǝv���܂��B 1998�N�ȍ~�͗A�o�̑���ɂ��A�o���i�̍����ɂ�荑�����i���㏸���A���Y�ʂɑ��鍑������ʂ̊������R�O���i�����P�l����̏���ʂR�O�����߂��j�ɒ����ɋߕt���Ă��Ă��܂��B���̑���Ɍ{���̏������I�ɑ����Ă��Ă���A2005�N���ɋt�]���܂����B����͐��\�N�O�̃A�����J�̏Ɠ����ł��B ���݂ɉߋ��̍�����l����̎q�������܂ދ����̏����<�}���x�[�X>�̐��ڂ́A1960�N39kg�A�@1970�N40kg�A�@1977�N70kg�A�@1980�N45kg�A�@1990�N40kg�A�@2000�N38kg�A�@2004�N36kg�Ƌɂ߂ď������ł����A�����Ɍ������Ă��܂��B ���b�h�~�[�g�i�r�[�t������}�g���j
↘�@�@ �@�z���C�g�~�[�g�i�`�L����|�[�N�j�@↗�@ �H���̏���X���́A���̏@�卑�C�M���X����̓`���I�ȐH���Ƃ����鋍���A���Ƀ�����}�g���������X���ł���̂ɑ��A�{���͂͂�����Ƃ���������A�ؓ��͑Q���X���ƂȂ��Ă��܂��B�܂�A�����J���łȂ��ɂ���A�z���C�g�~�[�g�n�D���傫���i�s���Ă��܂��B ���̉~�O���t��1967�N��2008�N���r���Ă݂�ƁA����40�N�]��ŃI�[�X�g�����A�l�̐H�������h���X�`�b�N�ɕω������̂��킩��܂��B���Ȃ킿�A�����E�}�g���̏���{������ɂقڊ��S�ɒu������������Ƃ������ƂȂ��Ă��܂��B2005�N�ɂ́A���Ɍ{�����������H������̑��ʂƂȂ�܂����B���̌X���͍�����X�ɐi�s����ł��傤�B ����S�̂̐H������ʂ��������ɂ�������炸�A�����̏���ʂ͒����Ɍ������Ă��܂��B �܂�2008�N�ɂ͐H���̑S��Ƃ�����ʂ��������܂����B����͈��������H���̉��i�����ւ̔����Ǝv���܂��B
�f�[�^�\�[�X�FABARE �H���̎�ޕʏ����(�P�ʁF�����}���ް�)
�f�[�^�\�[�X�FMLA �Ȃ��I�[�X�g�����A�ł͓ؓ��̓e�[�u���~�[�g�i�����j�Ƃ��Ă̏���͕č��Ɠ��l�ɔ��ɏ��Ȃ��̂ł��B�唼�̓n���E�\�[�Z�[�W�ɉ��H����A�������N�������������i���L�тė��Ă��܂��B���������̂قƂ�ǂ�2,100���̐l����w�i�Ƃ������������ł���ׁA�ؓ��̏���̐L�т͋߂��������ł��ɂȂ�ƍl�����܂��B �Q�l�܂łɃI�[�X�g�����A�̓ؓ���������x�[�R���́A�C�M���X�Ɠ����悤�ɁA���^�̎}���������Ƃ�����t���A���[�X�c�t���̂�����u�T�C�h��x�[�R���v���唼�ł��B�������������ł̓̂ƒ{��������ʓI�ł���ׁA�ʏ�Y�̋����͍s���܂���B���̂ق����u���̏d�v���傫���A�����������ǂ�����ł��B �Q�l�F��v���̋�������� �ȉ��͂Q�O�O�O�N�̐��E�̎�v���ł̋����̍�����l������̏���ʂł��B�P�ʂ͎}���d�ʊ��Zkg�ł��B ��āA�k�āA��m�B�A���[���b�p�ȂNj����̐��Y�ʂ��������́A��l������̏���ʂ���Ⴕ�đ傫���Ȃ��Ă��܂��B���{�ȂNj����̏���ʂ̏��Ȃ���i���́A����ނ�z���C�g�~�[�g(�ؓ��A�{��)�Ȃǂ̑��̓����^���p�N�̏���傫���Ȃ��Ă��܂��B
�f�[�^�\�[�X�FUSDA b) �O���C���t�F�b�h��r�[�t�̏����
�O�ɂ��q�ׂ܂����悤�ɁA�I�[�X�g�����A�����ł̓O���X�t�F�b�h��C�[�����O��r�[�t���`���I�ɍ�������̒��ƂȂ��Ă��܂����B�������O���C���t�F�b�h�igrain fed�������j�r�[�t���A�����Q�O�N�̊Ԃɏ������V�h�j�[�A�����{�����Ȃǂ̑�s�s�𒆐S�ɐL�тĂ��Ă��܂��B���������̍����������͕ʍ��������悤�ɍŒ�70���ƂȂ��Ă���A�ʏ��70�`80���̃P�[�X�������Ȃ��Ă��܂��B�}���d�ʁiHSCW�j�͂���ʓI�ȃO���X�t�F�b�h��C�[�����O��150-170kgs�����d��170-210kgs�ƂȂ��Ă��܂����A����ł����{������300kg�ȏ�̎}�����Q��菬���Ȃ��̂��唼�ł��B�I�[�X�g�����A�ł͓��{�̂悤�ɃX���C�T�[���g�p���Ȃ��̂ŁA�X�e�[�L(����)�̏�Ԃł��_�炩�ȐH�������߂�X���������Ă��܂��B c) �����̍�������ƏB�ʂ̗A�o�ˑ��x�̊֘A
�f�[�^�\�[�X�F
�Q. �����ƂƏ���`��
a)
�����ƊE�̊T�v
1993�N�̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�ƐH�����X(��������)�ʂ̐H���S�̔��ɂ�����S�����σV�F�A�͑O�҂��S�R.�P���A��҂��T�U.�X���ƂȂ��Ă��܂��B�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̃V�F�A���N���ɏ��������サ�Ă���A1995�N�ɂ̓X�[�p�[�}�[�P�b�g�̑S�����σV�F�A���قڂS�T���ƂȂ�܂����B���̌�2008�N��MLA�̓��v�ł́A�e�[�u���~�[�g�̔̔��̓X�[�p�[�}�[�P�b�g���S�̖̂�Q/�R���ߎc�肪���X�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B �X�[�p�[�}�[�P�b�g�͔N�Ԗ�R�T���g���̋����E�����E���B�[���E�|�[�N������Ă���A�Ȃ��ł��R�[���Y(Coles:Myer�܂�)�A�E�����[�X(Woolworths�A�ʏ́hWoolies�h)�Q�Ђ͂����̒��ł��Q�������ʂ������Ă��܂��B�i��R�ʂ̓t�����N�����YFranklins�j �Ȃ��O�H�Y�Ƃŏ����ʂ͑S�̖̂�3���ƂȂ��Ă��܂��B (1)
�E�����[�X(Woolworths)�̊T�v
�C���e�O���[�V���� ���ɃE�����[�X���A����L���g���o�C���[��i���A�t�B�[�h���b�g�ƐH���p�b�J�[�Ƃɑ���ʂ̔�狍�Ƌ������ϑ����Y�����Ă��܂��B�܂艵����ʂ������ڍw���̕������Ƃ��Ă���A���{�̐̂̃_�C�G�[�Ɏ��Ă��Ȃ����Ƃ�����܂���B ���Ђ͉ߋ��T�N�ԂŔ��オ�قڔ{�����Ă���I�[�X�g�����A�ő�̐H�������ƂŁA�e�B�Ɏ���̐H�����H�Z���^�[�������Ă��܂��B�N�C�[���Y�����h�B�ł̓C�v�X�E�B�b�`�ɏB���̂p�`�b�iQueensland Abattoir Corporation�j�̎{�݂���āA�uBrismeat�v�Ƃ������O�ŏW�z���H���s���Ă��܂��B�N�Ԗ�500,000���̋����w�����A�N�C�[���Y�����h�B���̑S�X�[�p�[�̐H���̔���46%�̃V�F�A�������Ă��܂��B����͓��B���̑S�ԓ��itotal red meat�j�̔��̃V�F�A�ł�18%�ɓ�����܂��B 2008�N�ɂ͓��Ђ̐��N�����̔��V�F�A�́A�S�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̖����߂�Ɏ���܂����B �H���̔��̊T�v �����i�{�������j����ւ̂P�T�ԓ�����̗��q���͖�S�O���l�ŁA�ł�����鏤�i�̓r�[�t100%�̔҂�����beef diet mince (95CL)�ŁA�N�Ԕ���͂P�Q�S�����h���ƂȂ��Ă��܂��B �ȉ��ɓ��X�[�p�[�̔̔��i�ڕʂ̓���������܂��B��S�ʂ̐��\�[�Z�[�W�̓I�[�X�g�����A�����̖�O�o�[�x�L���[�̑O�Ƃ��Ă�����ʓI�Ɏg������̂ł��B�ܘ_���C���f�B�b�V���͑�P�ʂ̃r�[�t�ŁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�X�e�[�L�Ƃ��ď����܂��B�Ȃ����̖�O�o�[�x�L���[�iAustralian Barbecue�j�͌l�̒��A�����Ȃǂŋɂ߂ĕp�ɂɍs���Ă���A���̏���ʂ͌����Ė����ł��Ȃ����̂�����܂��B 1. �r�[�t�i�������j �F43.4% 2. ���� �F18.0% 3. �|�[�N �F10.6% 4. ���\�[�Z�[�W �F 9.6% 5. �`�L�� �F 8.2% 6. �n���E�\�[�Z�[�W �F 7.5% 7. ���B�[���i�q�����j �F 1.5% 8. �}�g���i���r���j �F
1.2% �܂����Ђ̌��J�f�[�^�ɂ��Ə���҂̂P�l������̐H���w���͈ȉ��̒ʂ�ł��B l ���X���͏T2.3�� l �����̍w���ʂ�2.4�p�b�N�ŁA���z�ł�A$10.80 l �N�ԍw�����z��A$1,292 (2) �R�[���Y(COLES)�̊T�v
����ƊE��Q�ʂ̃R�[���Y�͎�Ƀx���_�[�ivendor�H�������Ǝҁj����r�[�t���d����Ă��܂����A�I�[�X�g�����A����J���g���[��`���C�X��(Australian Country Choice Co.)�͂��̑�\�I�Ȃ��̂ŁA���Ђ̓L���m���q���ł̑��Ƃɉ����A1996�N7���r�[�t�����Y��(Beeflands)����N�[�~�j�A(Coominya)�H����B1997�N����̓I�[�X�g�����A�}�N�h�i���h�����Ƀn���o�[�K�[�p�e�B�[�̋������J�n����ȂǁA���͂��g�債�Ă��܂��B b)
�X�[�p�[�}�[�P�b�g�ł̏���ғ���
ASI�iAustralian Supermarket Institute�j�́A�I�[�X�g�����A�̃X�[�p�[�Ƃ̋���ŁA�R�[���Y��}�C���[Coles Myer Ltd., �f�C�r�b�hDavids Ltd., �t�[�h�����hFoodland Associated Ltd., �t�����N�����YFranklins
Ltd., �W���E�F���t�[�hJewel Food Stores Ltd., �E�����[�XWoolworth Ltd.�̍ő��T�Ђ������o�[�ƂȂ��Ă��܂��B���̂T�ЂŖ�5,500�̓X�܂������A�I�[�X�g�����A�̑S�X�[�p�[�}�[�P�b�g����̖�95%�̃V�F�A���ւ��Ă��܂��B 1996�N��ASI�ɂ��1,000�l�ւ̓d�b������蒲���ɂ��ƁA�I�[�X�g�����A�̏���҂̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�ł̏���s���Ɨv�]�́A�ȉ��̂Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B
1996�NASI l ����҂̒��ōł������̂͏����ŁA���ϔN��͂S�O�ˁB l �ؗj�E�y�j���̔������͌���X���ɂ���A�j����I�Ȃ��X���������Ȃ��Ă��܂��B�i1994�N16%��1996�N21%�j l �������͔̉����ȏ�̐l���T�P��ōς܂��Ă���A���{�̂悤�ɓ��p�i�̔������Ɏ��Ԃ������Ă��܂���B l �������̎��ԑтɂ��Ă͌ߑO�����ł������A�ߌ�T���ɏW��������{�Ƃ͈���Ă��܂��B�I�[�X�g�����A�l�͉��X�ɂ��Ē��N���̐l��ł���A���Ɍ���J���҂͌ߌ�R���ɂ͎d�����I���āA����ȍ~�͉ƒ�̎G�����s���̂���ʓI�ł��B(�f�X�N���[�J�[�͂T���܂Ŏd���B) l ����҂̊S���́A���{�Ɠ������a�����咰�ہi�I�[�X�g�����A�ł�0�111�j����������������A���S���A������a�Q�ۂւ̐S�z���ł�������73%�ƂȂ��Ă��܂��B l �X�[�p�[�ɖ]�ގ��Ƃ��ẮA�̂�т肵���������Ƃ��Ă͈ӊO�ȁA�u���W�̎��Ԃ̒Z�k���v��18%�ƍō��ʂƂȂ��Ă��܂��B c)
�����̍w������
���ɃV�h�j�[�A�����{�����̂���H�����X�ł̃r�[�t�̕��ʕʍ\����Ɖ��i�͈ȉ��̒ʂ�ł��B���̐����͍�����傫���ω����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B �H���X�ɂ����鋍���̃A�C�e���ʍ\����(1992�N�ĥ�~����)
d)
�H���̕��ʕʏ������i
�ȉ��ɁA2008�N3�����_�ł̃V�h�j�[�ɂ����鏬�����i�������܂��B ���i�@�͍��B�h���^�L���O��������A�A�͉~���Z�i���W�O�^A$�j�^100�O��������ƂȂ��Ă��܂��B
������2008�N11�����ư�����X�ł̉��i�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
���F�X�R�b�`�t�B���b�g���L���[�u���[���A�@�בւ�80�~/���B�h���Ōv�Z e)
�ƒ�ł̒������@
�I�[�X�g�����A�̉ƒ�ɂ����钲�����@�͉E�̒ʂ�ł��B�@
�܂��u�Ă��v�̒��ɂ́A���Ȃ�̌ˊO�o�[�x�L���[�iAustralian Barbecue =Aussie
Barbie�j���܂܂�Ă���A���̉ƒ�̒�ɂ͑�^�̃o�[�x�L���[�ݔ�������A�����ʼnƑ���e�����l�ƏW�܂��ĐH��������̂��N���s���ɂȂ��Ă��܂��B �Ȃ������Ă��̂͒���̌W�ŁA������̓T���_��f�U�[�g��S�����܂��B�ʏ��Еt���͒���Ǝq���������s���܂��B ���t�H�[�}���ȃo�[�x�L���[�𗈕o������ɏ����s���ꍇ�́A���傪�������Ɠ����Ă��ԁA���l�̓C�u�j���O�h���X�Ń��C���O���X��Ў�ɗ��q�Ɗ��k����̂��A�I�[�X�g�����A���Ȃ̂ł��B�@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||