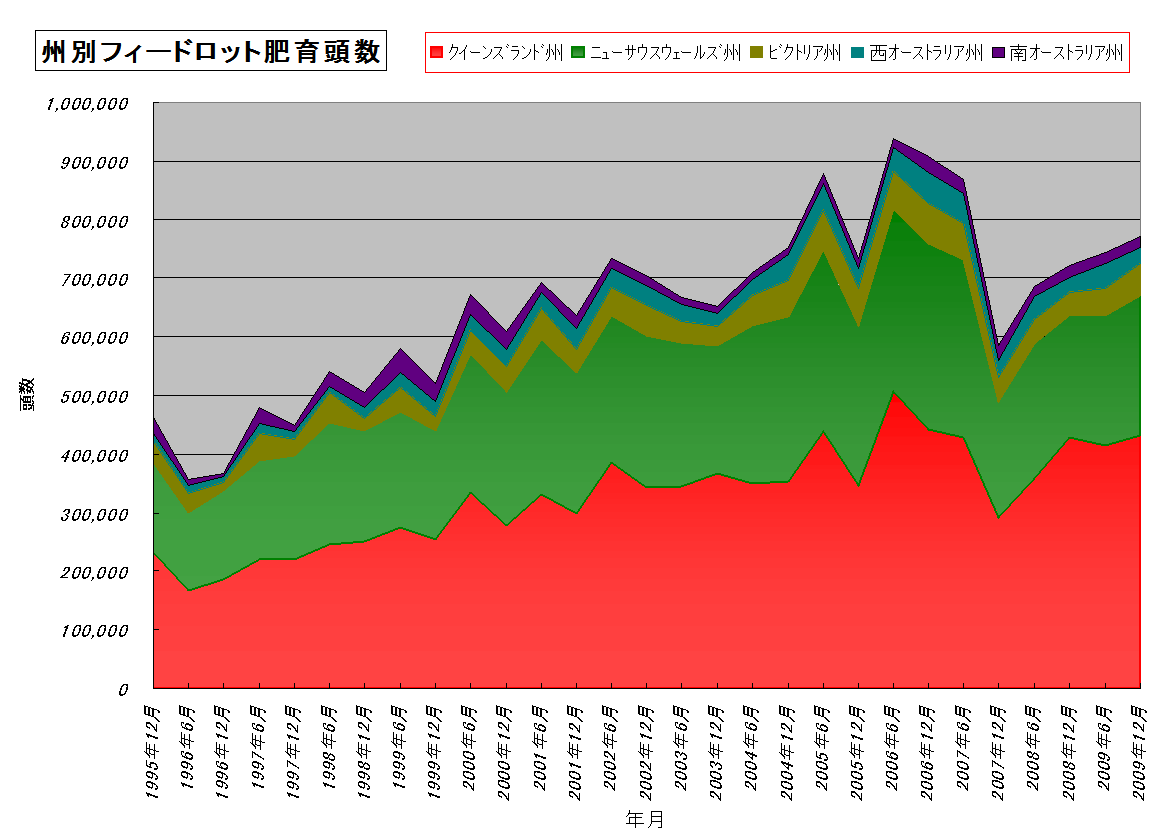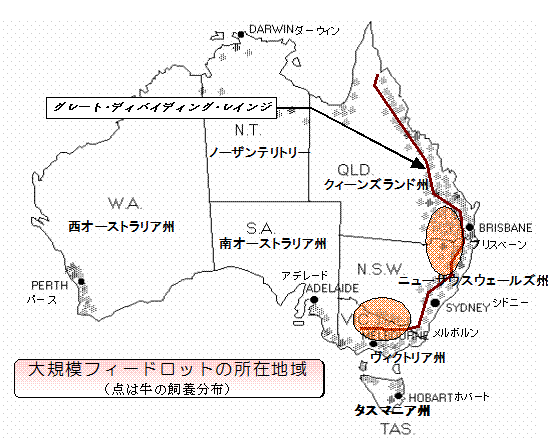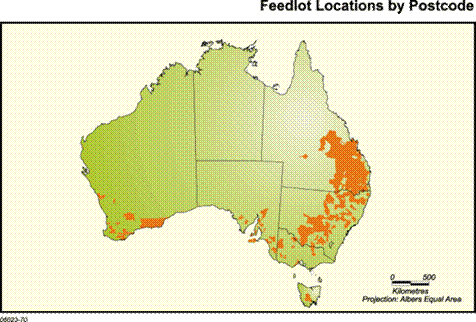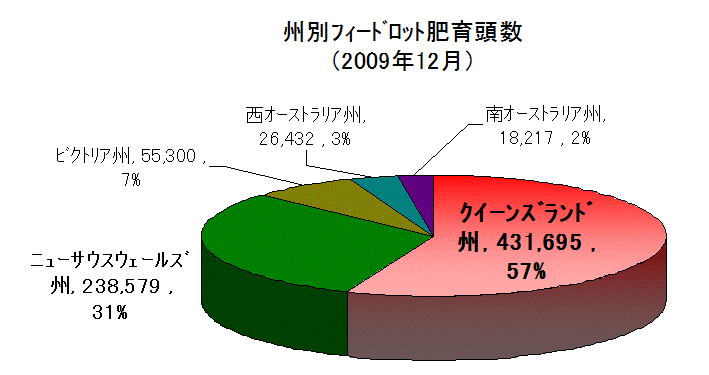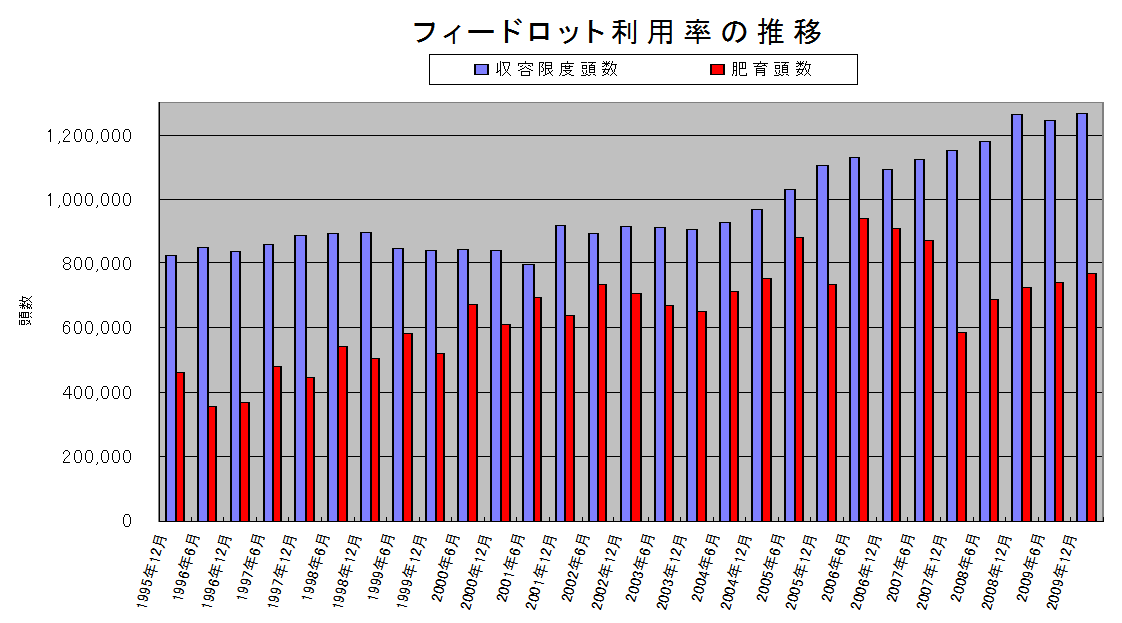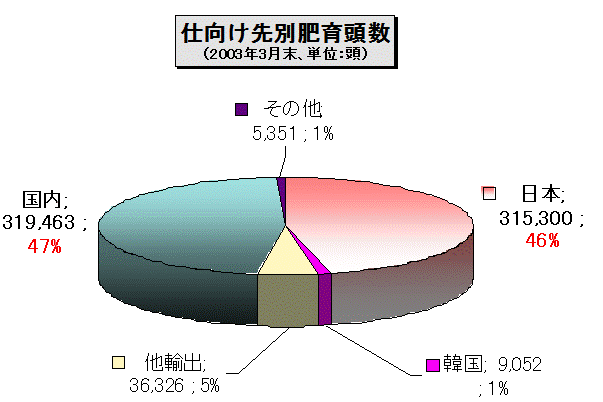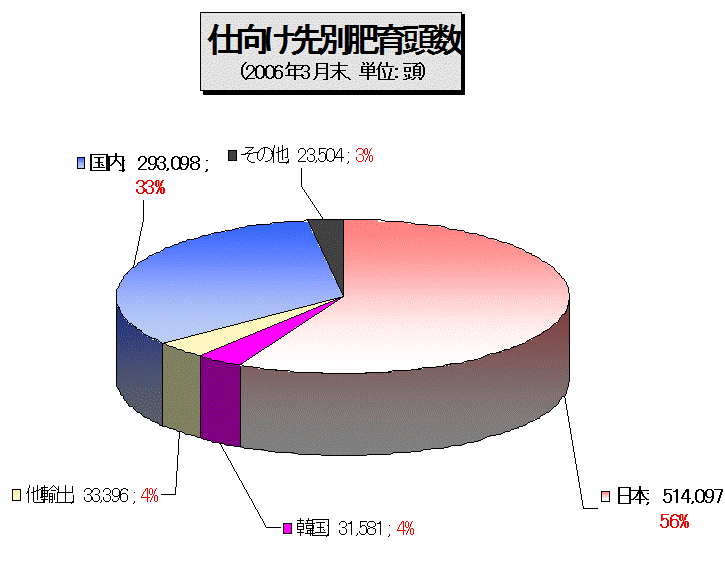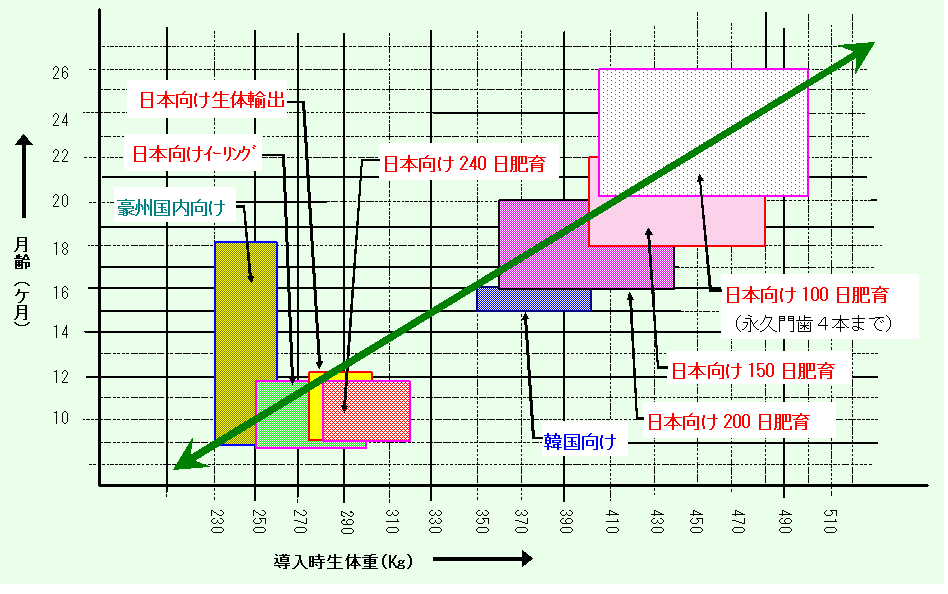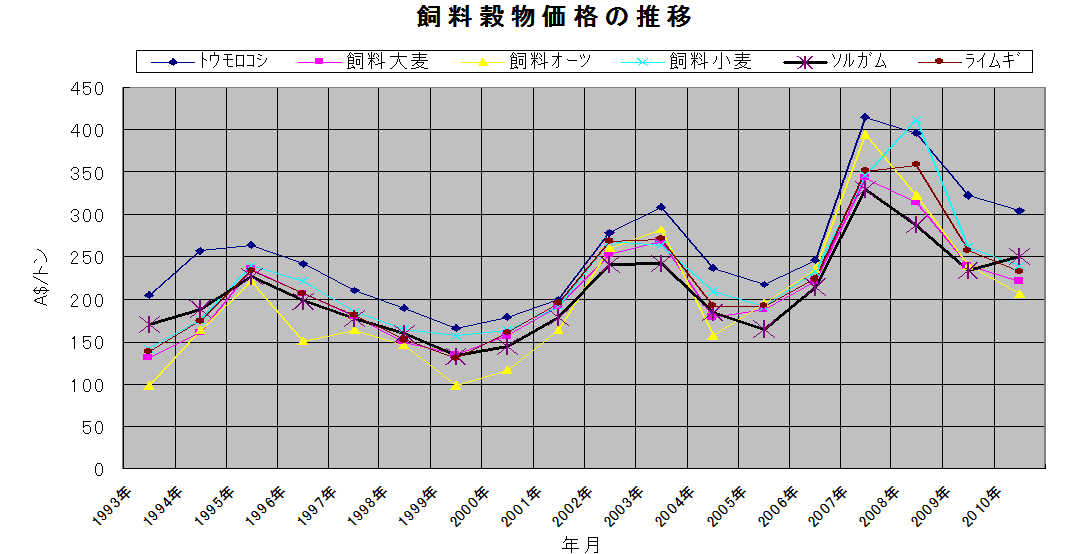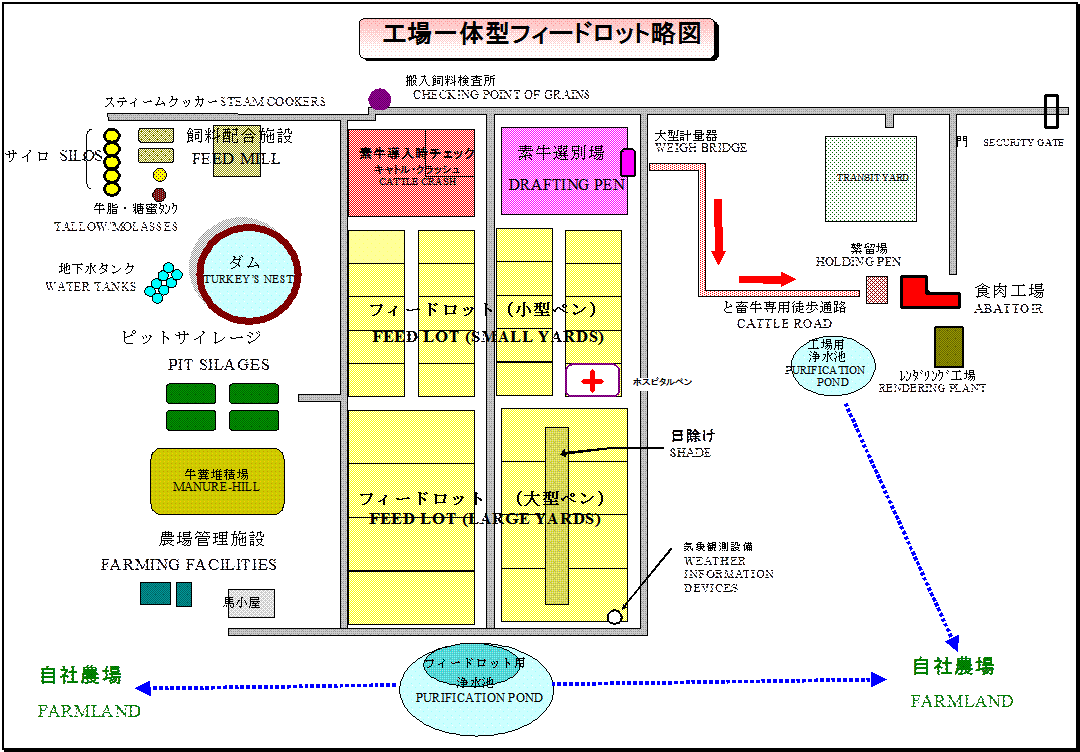1.
日本マーケットを目指して
肥育業者が牛を肥育する為、柵で土地を区切り、その中に牛(肥育素牛という)を導入し、穀物で肥育する場所をフィードロット(feed lot)といいます。 大別して多頭肥育・商業生産を目的とした「コマーシャル・フィードロット (commercial feedlot)」と、農家の小規模・不定期肥育による「オポチュニティー・フィードロット(opportunity feed lot)」(米国の「ファーマーズ・フィーダー」にあたります。)に分けられます。 オーストラリアでは特に日本向けのビーフの肉質の向上を目的とするだけではなく、両者とも降雨量の不安定に起因する生牛の価格変動のリスクをカバーする目的が、その存在の第一の理由と言えます。オポチュニティー(機会)・フィードロットというネーミングそのものがこれを明確に表しています。 つまりオーストラリアにおけるフィードロットはアメリカとは違い、以下の独特な理由で作られてきたのです。 1.
干ばつなど牧草の不足に対応するため (国内向け肥育も含む) 2.
脂肪交雑(marbling「霜降り」、「サシ」)を重要視する日本市場向け 3.
輸出向け、国内向けの牛の品質を均一化するため。(米国と同じ) a) フィードロット建設の歴史
第1号の日本向けフィードロットは1960年代トゥーウンバ(Toowoomba,ブリスベーン西方約130Kmの内陸都市)近郊に建設されました。 この20年を振り返ると概ね2回のフィードロット数の増大時期があり、その2回ともが主に日本資本のコマーシャル・フィードロットの建設によるものでした。即ち、1975年の第1次オイルショック直前に約10社がオーストラリアに大挙した後、世界的な景気後退のためその殆どが撤退を余儀なくされた(三菱商事はキララ・フィードロットを縮小しながらも継続。後にミドコミートを買収したが結局撤退。)のが第1期であり、第2期としては、1988年6月のビーフ輸入自由化発表後(自由化後ではない)に再度急増し今日に到っているものです。 b) フィードロットの規模の推移
2002年現在、オーストラリアにはオーストラリアフィードロット協会(ALFA−Australian Lot Feeders Association)が認定するフィードロットは約598ヶ所(認定外も含めると千ヶ所以上)あり、これらには約86万頭の牛が肥育されています。 1990年以降(第2期以降)のフィードロット規模の推移は次のグラフのとおりです。
データソース:MLA 1995年頃は約40万頭がフィードロットで肥育されて(収容限度頭数約80万頭)いましたが、その後は海外からの需要増に対応し少しずつ増加し、2002−2003年には70万頭と倍増しました。2005年時点ではBSE発生により米国からの牛肉輸入が停止したためと、日本経済が回復基調にあり、更には干ばつの影響で約90万頭(収容限度頭数約110万頭)もの牛がフィードロット肥育されるようになりました。 しかし2006-7年になると、主に日本での牛肉価格高騰による消費の減少と、豪州ドル高と穀物価格の上昇による輸入コストの上昇が影響し、肥育頭数は大幅な減少に転じました。 この時期にはフィードロットの利用率は急激に低下し、かつて70−80%であったものが、約50%にまで急降下することになりました。この急落はオーストラリアのフィードロット始まって以来の大きな変化でした。その後はやや回復し漸増に向かっています。しかし穀物価格は落ち着いたものの、豪州ドル高の基調は変わらないため、日本向け輸出に大きな改善は見られず、肥育頭数は以前に戻ってはいません。 ところでフィードロットでの肥育頭数は全飼養頭数の約3%にしかあたらず、米国に比べ未だ非常に少ないこともオーストラリア畜産業の特徴です。参考までに、米国には32,000頭以上の大規模フィードロットは118ヶ所あり、大手フィードロット上位10社のそれぞれの収容能力は、200,000頭から約500,000頭となっています。これは豪州の数倍以上の規模となっています。 なお牛肉生産量の比率では約14%(1993年)がグレインフェッドとなっています。また日本向けと国内・米国向け枝肉重量の格差は著しく、米国での状況との違いが如実に現われています。 c) 州別肥育規模とその推移
地域的には、下の図に示すようにクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の比較的乾燥した内陸部とくに穀物・水資源の豊富なダーリングダウン周辺地域(特にクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の州境)、及びマレー川流域(同様ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の州境)に大規模フィードロットが際立って多くなっています。この両州だけで全体の約80%のフィードロットをカバーしています。
ANRA
厳密には1988年‐1991年までは前者の地域に多かったのですが、1992年以降は後者の地域に多く建設されるようになりました。これには1992ー1995年継続した長期的な旱魃の中で被害が少なかったマレー川流域では、日本バイヤー好みの英国種と穀物の供給が比較的容易であったからと考えられます。この地域では多くのフィードロット建設計画があり、今後両州の数値はかなり接近するものとみられます。
データソース:MLA 51% 83% d) 仕向け地別の割合
仕向け先別の肥育頭数は、1992年では圧倒的に日本向けが多く、第一位日本、第二位オーストラリア国内、第三位韓国の順となっていました。 しかし2003年になると、日本向けが大幅に減り(65%→46%)、国内向けが増えて(21%→47%)います。これには以下の理由があったと考えられます。 1. 2.
データソース:MLA しかしその後2003年12月、日本向け輸出におけるオーストラリアの最大の競争相手である米国にもBSEの患畜が発見された為、米国からの牛肉輸入は停止されました。このため再び日本向けの肥育は増大し、2006年になると再び、約半数以上の牛が日本向けに肥育されるようになりました。 なおフィードロットにとり重要なリスクヘッジとなる、カスタムフィーディング(custom feeding=委託肥育)は全体の20〜25%と推測されます。 2.
仕向先と経済性
過去韓国が本格的にオーストラリアビーフを買い付ける以前、フィードロットが導入する肥育素牛の生体重は2種類に分かれていました。ターゲットとする肥育仕様は大きく分けると、枝肉重量約200kgの国内向けと同300kg以上の日本向けの2つに分かれており、肥育業者は大きな相場リスクを抱えながら操業していました。しかし韓国からの発注が増大してからは、韓国向けが国内向けと日本向けの間に位置するようになり、より安定した仕入れと販売が出来るようになりました。つまり経済効率がかなり改善することになりました。 導入時生体重と月齢の関係をシンプルに図解すると以下のようにほぼ切れ目がなく、無駄の少ないリスクヘッジのできる構造となっています。 勿論それぞれの仕向け用の肥育の最終仕様には、枝肉重・月齢(永久歯の数)とも上下の幅(allowance)があるからです。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
ただ厳密にみると、この構造は上の相関関係図に示すように、さらに「オーストラリア国内向け」〜「日本向け240日」のグループと「韓国向け」〜「日本向けショートフェッド」グループの2つのグループに分かれていることが分かります。すなわち前者が生体重約200〜300Kg・月齢1年であるのにたいし、後者は300〜500Kg・1〜2年となっています。それぞれのグループには、前者には「オーストラリア国内向け」、後者には「韓国向け」及び「日本向け100日肥育=ショートフェッド」という『すべりどめ』ともいうべき仕向け先用の群がおり、肥育の無駄がないような購入システムとなっています。 参考までに米国での生産に関しては、圧倒的に多い国内向けと、同国輸出先第1位である日本向けは基本的には同じ規格の枝肉を使用している為、オーストラリアのような問題は通常全くありません。 ただ一部の業者は、日本向けに米国の通常の約100日肥育の生体に更に追加肥育している為、所謂ハードボーン(hard
bone)問題が出てきます。米国のグレーディングでは、追加肥育することで枝肉の軟骨が硬骨化した枝肉は格付けの成熟度(maturity)条件で減点され評価が下がることが多いのです。 3. 穀物価格の推移
2007-2008年には所得上昇にともなう中国等の途上国飼料需要の拡大を背景に、干ばつ、凶作や米国におけるバイオエタノール需要の急増、投機資金の流入などに影響され、主要穀物がいずれもかつてないほど高騰しました。 こうしてロット・フィーダーにとっては、日本向け肥育の条件の一つが改善されましたが、豪州ドル高は相変わらずで、輸出価格を押し上げているため、肥育頭数の改善が今ひとつとなっています。
4. 環境問題とフィードロットの構造
次にフィードロットの構造見取図を下に示しておきます。これはフィードロットと食肉工場一体型の例で、給餌・汚水処理・病疫対策・個体管理など必要な事がすべて一元管理されている事が図中に見て取れると思います。
大型のフィードロット全てに共通しているのは、特に汚水処理関係で十分な対応が施されていることです。各ヤードまたはペンpen(区画)は降水時に汚水が流れ易いように必ず傾斜地が選ばれます。ヤードの下には間を堰で2つに仕切った汚水処理池(purification pond)があり、汚水が池の片方に溜まると上澄みが堰をオーバーフローして、もう一方に流れ込むようになっています。この上澄みの部分をフィードロットの敷地内の畑又は緑地に散布するよう義務付けられているのです。 つまりフィードロット内の汚水は全て自所内で処理するようになっており、一般河川や地下水に流れ込まないよう厳重に設計されています。従い食肉工場との一体式施設については、汚水処理が工場排水とダブルになる為、許可取得は非常に難しいのです。新設のフィードロットが人里離れた場所に建設される由縁です。 このように近年は環境問題のため民家のある地域での建設は非常に困難になっているのが現状で、幾つかの環境汚染に関わる訴訟問題も表面化しています。 またフィードロットの中に「ホスピタル・ペン」と呼ばれる隔離区画があります。病気と疑われる牛については即座に他の牛と隔離してホスピタル・ペンに入れ、専門の獣医の診断を受け治療されます。問題の無い病気の場合は治ってから元のペンに戻されます。こうした生体の24時間管理体制のため通常は生畜専門家が敷地内に家族とともに常駐します。
因みに1993年現在の規定では、1頭当りのフィードロットのスペースは12m2〜16m2となっています。なお牛のと畜の方法についてもRSPCAの存在は無視できません。 またフィードロットの建設費用については、収容限度が300頭で特別な建設許可条件が必要ないものについては約100千豪ドル(1頭当り約330ドル)であるのに対し、収容限度が10,000頭のフィードロットは約6,000千豪ドル(同約600ドル)と1頭当りの建設費用が約2倍かかります。 因みに1993年度(1993.4-1994.3)に全オーストラリアの5,000頭以上の規模のフィードロットで消費した飼料は、グレイン約1.4百万トン(大麦0.8, 小麦0.4,
ソルガム0.2百万トン )・粗飼料約0.7百万トンの計約2.1百万トンでした。一方でオーストラリアは穀物の輸出をしていますが、ソルガム・大麦など品目によっては全生産量の2〜5割を自国の--フィードロットで消費しています。最近ではフィードロットの収容キャパが増大しており、折りからの旱魃の影響で穀物の不足と相場の高騰が生じています。このためフィードロット業界からは非加熱飼料輸入の要望が高まり(加熱飼料は価格が高い為、サンプル輸入で終わった)、これに反対する穀物生産者との間で確執が生じています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||