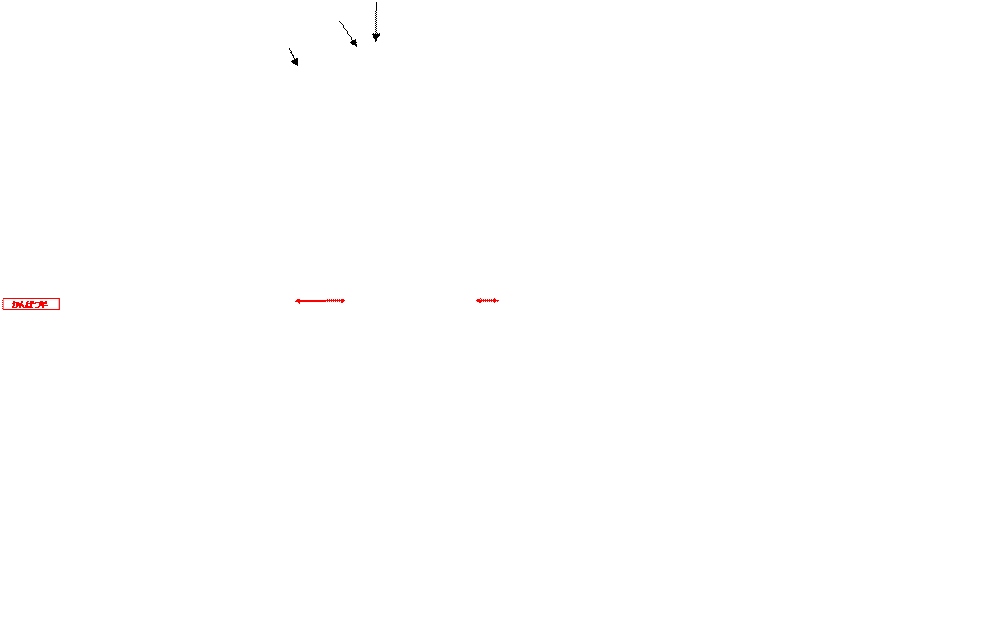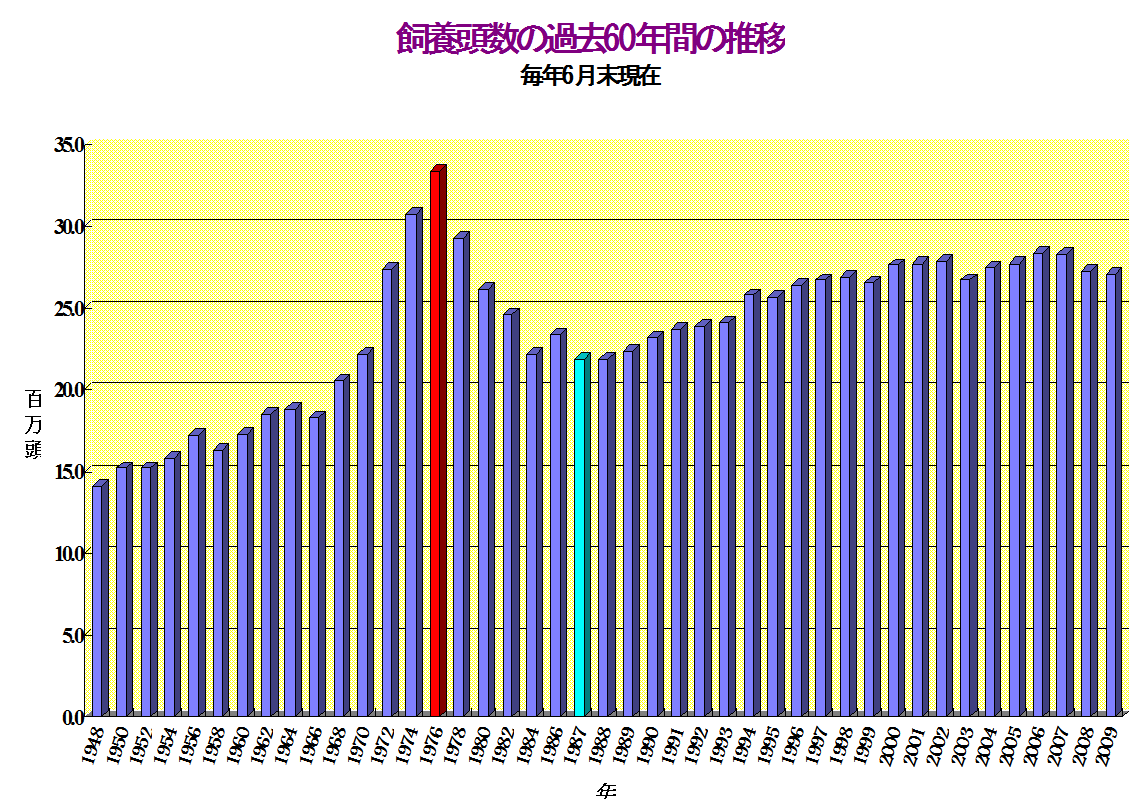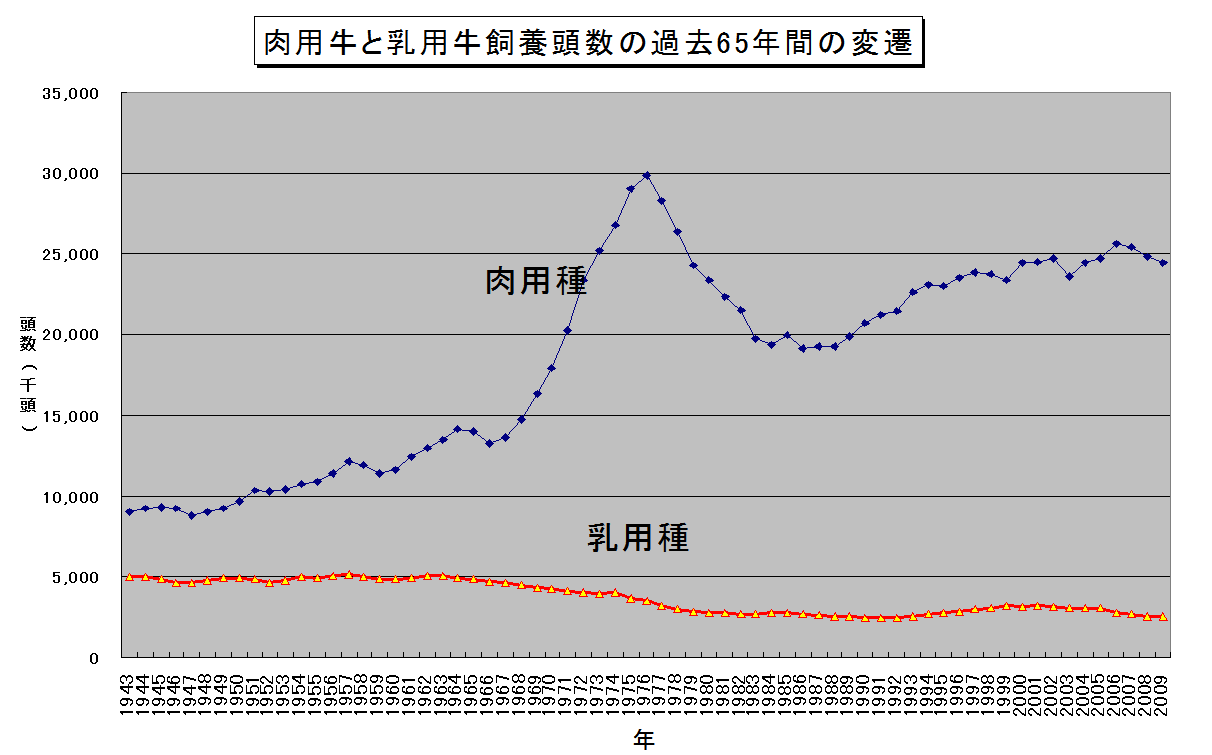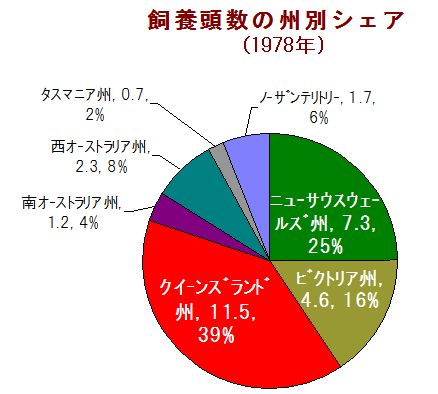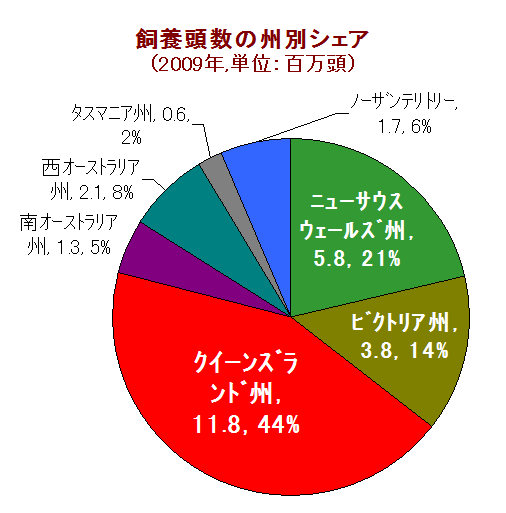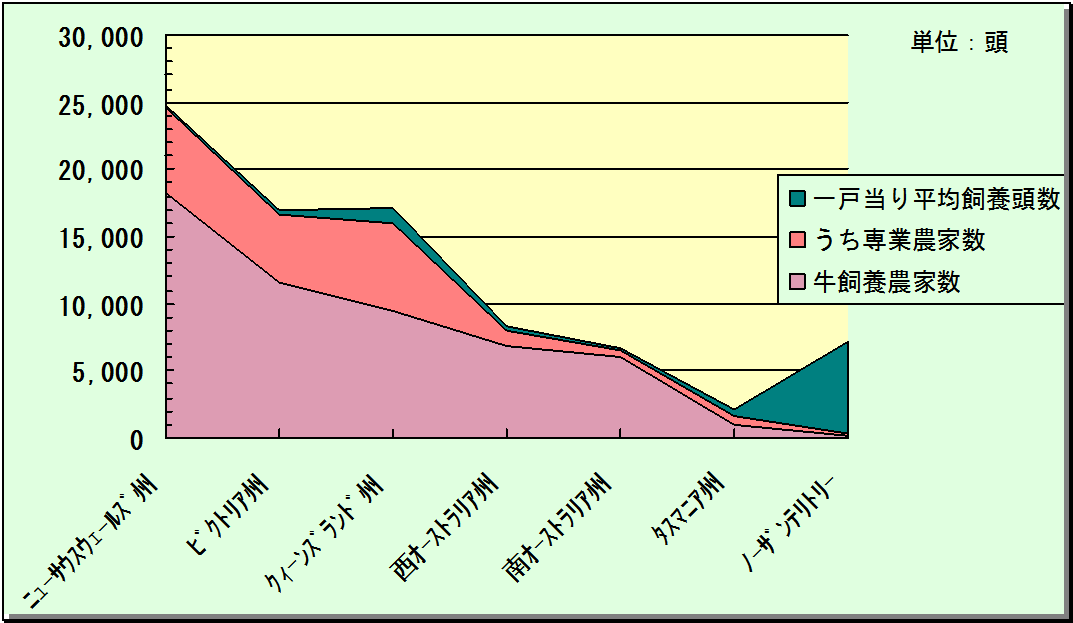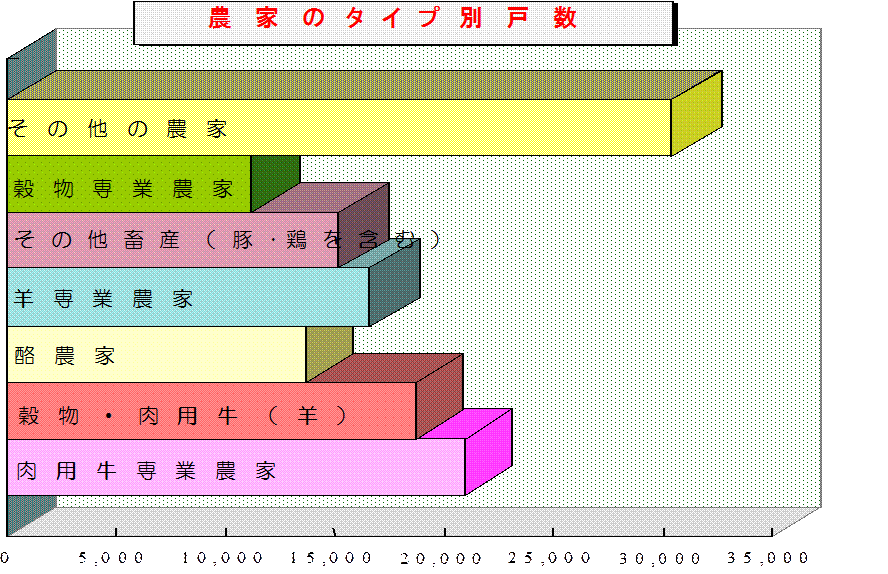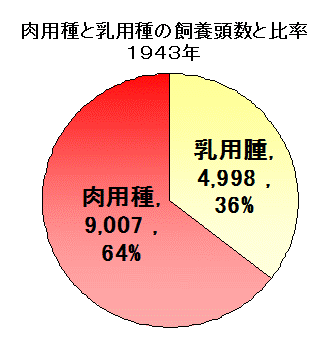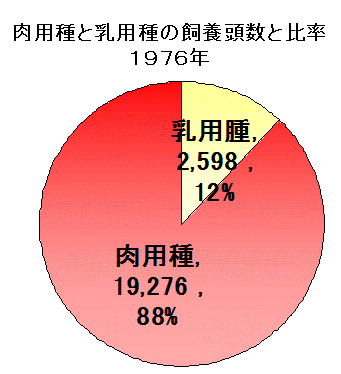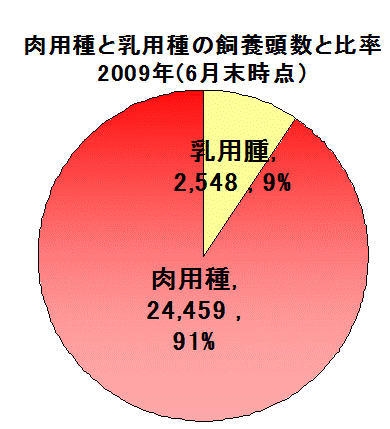1. 全国的な動向
克服されつつある旱魃の影響 日本輸入自由化 BSE発生・拡大 世界同時株安 不況 日本高度経済成長 オイルショック
データソース:MLA他 牛の飼養頭数は、過去の経過が端的に示しているように、降雨量と海外市況の2大要因に左右されてきました。(3番目が国内消費です。) これはオーストラリアのビーフ産業のもって生まれた宿命であり、牛肉の流通の国際化が進行する中で、今後解決しなければならない最重要課題でもあります。そこでこの2大要因の影響をベースに、一例として以下1950年以降約60年間の動向を追って、オーストラリアの飼養頭数の増減を分析してみます。 1950〜1970年 1950年から1960年代前半まで、飼養頭数は1,500〜2,000万頭で推移しました。この間1958年から1967年までは極めて長期の旱魃状態にあり、飼養頭数の伸長は抑えられていました。 しかし1968年旱魃が終わると飼養頭数は俄然増え続け、一方日本では高度経済成長期に入り、輸入が促進されました。 1970〜1990年 1970年代中期、海外の牛肉需要の増大を受けてタチ(牛の生体のこと)生産業者の牛群増大意欲が更に向上し、増加傾向を示していました。 ところが、1975年に世界的な石油危機により海外への輸出需要が急激に減少し、と畜(家畜を屠殺すること。日本の業界では「屠畜」とは言わず「と畜」とするのが慣例です。)頭数が激減することになりました。この結果、飼養頭数はそのまま増え続け、1976年には3,340万頭と飼養頭数はオーストラリア史上最高を記録しました。(グラフ中の赤の棒) 海外需要が急激に減少して輸出が大いに低減したため、牛肉価格は下落し国内消費量が急増し、国民一人当たり消費量は1974年55キロ、1976年66.4キロとなり、1977年にはついに70.3キロを記録しました。 翌1977年になると米国、日本等への海外の需要が回復に向い、輸出市場は再び活気を取り戻し、と畜頭数が急速に増加しました。そのため飼養頭数は反転してキャトルサイクル(飼養規模の増減サイクル曲線)の谷に向って漸減しました。 1980年代初頭大旱魃の長期化により生体(特に経産牛=dry cow, cull heifers)の淘汰が進み、加えて牛肉生産の利益率の低下から他産業(穀物生産)、他畜種(羊)への転換が進行し、1984年には2,220万頭とこの9年間で1,120万頭(34%)の減少になりました。 1987年にはほぼ10年前の水準まで減少し(グラフ中の水色の棒)、それ以降はようやくキャトルサイクルの谷を脱し緩慢な増加基調に移りましたが、米国を中心とする輸出マーケットの縮小及び引き続く旱魃等の気候不順により、1992年までは2,400万頭止まりの増加となりました。 1991年初頭エルニーニョの影響で約10年ぶりの大旱魃が発生し、ほぼ1年の間クィーンズランド州とニューサウスウェールズ州では極端な雨量の減少に悩み、特にメス牛のと畜が急増しました。 時同じくして日本では牛肉の自由化を迎えており、このと畜の増大は輸出の拡大にも貢献することとなりました。 1990年以降 しかしながら特筆すべきことですが、その後たびたび起きた大旱魃の全飼養頭数に対する影響は意外に小さく、1993年3月現在の飼養頭数は2,356万頭と従来の傾向とは違い微減にとどまりました。その主な理由はニューサウスウェールズ州西部、クイーンズランド州西・北部における肉牛飼養管理技術の向上で、従来の斃死率約5%が最近約1〜2%に改善されたことと、ビクトリア州などのオーストラリア南部では比較的降雨が多かったことが主な理由となっています。従い1990初頭はなだらかな漸増傾向を示しました。 1994/5年についても旱魃傾向が続きましたが、こうした理由で飼養頭数のあまり大きな減少はありません。 さらに2002〜2003年にかけて100年ぶりの大干ばつに見舞われました。 この影響については、飼養頭数は2003年3月31日現在、前年比4.3%減の2,420万頭と見込まれています。 この大干ばつの試練により、オーストラリアは全体の飼養頭数維持の自信が確立できたと考えられます。つまりオーストラリアはこの数十年間で、従来は最も不可避であると考えられた干ばつの影響を最小限にする努力を払い、少しずつですがこれに成功してきているといえます。 2006年から2008年にかけ度々の旱魃に見舞われ、飼養頭数はやや減少しましたが、枝肉重量が着実に増えてきているため、実質的な牛肉生産量は減少せずむしろ漸増しています。 国内消費量は価格上昇とともに漸減しているため、豪州ドル高にかかわらずその分が輸出に回っている形となっています。 今後の飼養頭数の増減は、第2のファクターである世界の経済・政治動向により大きく左右されることになりそうです。特に2003年以降世界的に大きな影響を及ぼしたBSEは牛肉貿易の流れを変えました。オーストラリアはこの世界的な要請を受けて今後着々と牛の飼養頭数を安定的に増やしてゆくものと考えられます。 一方乳用牛は次のグラフのように年々少しずつですが、確実に減り続けています。政府としても牛乳の消費拡大キャンペーンをしていますが、漸減は極めてベーシックな傾向となっています。 なお参考までに日本の牛の飼養頭数は2002年現在、肉用牛約284万頭、乳用牛約173万頭の合計457万頭ですから、オーストラリアには日本の約5倍の牛がいることになります。
2.
州別の規模と経営形態について
クイーンズランドが最大の畜産州 州別には下右の円グラフが示すように、クイーンズランド州44%、ニューサウスウェールズ州21%、ビクトリア州14%の順で、上位3州で全体の約80%を占めています。
データソース:MLA これについて、過去に遡って分析してみましょう。 飼養頭数の推移では、1977年〜1987年までの10年間に於ける飼養頭数の減少は全国平均で30%でした。これに対し、ニューサウスウェールズ、ビクトリア両州は各々41%、31%の頭数減となっており、全国平均を上回っています。これは、これら両州に於いては、牛群飼養から他畜種・他産業への転換が比較的容易であったこと、及び国内大消費地(シドニー、メルボルン)での消費後退により、供給力が需要を上回った結果での牛肉産業の低迷と考えられます。 一方、クイーンズランド州においては21%と頭数の減少は小さく、総飼養頭数の40.1%を占めました。特に同州の輸出依存度は非常に高く、1991〜1995年に至る北部での旱魃の影響にもかかわらず、上の円グラフに見られるように同州への集中は更に顕著となっています。 北部ほど専業・粗放化、南部ほど兼業・集約化 更に州別に牛飼養業者(農家)数を見てみると、専業業者を含めた総牛飼養業者数ではニューサウスウェールズ州が18,240ヶ所と最大ですが、専業業者数では6,600とクイーンズランド州が最も多く、専業率も70%と主要3州中では最大となっています。 一戸当りの平均飼養頭数では全州平均は約450頭となっていますが、これを州別に見てみると各々大きい順にノーザンテリトリー 6,842頭、クイーンズランド州 1,010頭、ビクトリア州 321頭、ニューサウスウェールズ州 313頭、となっています。総飼養頭数の少ないノーザンテリトリーはおくこととして、クイーンズランド州がいかに大規模経営の中心地となっていることがわかります。これは気候および立地条件による産業の州間格差が大きな理由です。 ところでノーザンテリトリー,クイーンズランド州の北・西部では経営規模があまりにも大きい為、完全な飼養管理が行き届かないこともあります。ところでこの地域では毎年牛泥棒の被害が発生しており、被害総額は毎年数億円にのぼる為、副産物としての皮の価値が落ちるのを承知で焼印(branding)をやむなく押している業者が多いのです。
データソース: 総牛飼育頭数:1992年
データソース: 参考 農畜産業者数とタイプ別内訳 全国の農畜産業者の戸数(会社組織を含む)は、1990年〜1992年のあいだ年間2ー3%の割合で減少していましたが、1993年は126,600戸と前年とほぼ同数でようやく減少に歯止めがかかりました。一番多いのは肉用牛専業業者で20,900戸となっていますが、豚・鶏を含めた全畜産業者数は85,000戸となっています。また同年は世界的な羊毛不況により羊専業業者が前年比15%も減少し、これが肉牛および穀物専業業者などにシフトしました。一戸当りの年間売上では半数にあたる業者が10万ドル(約800万円)以下で、残り半数が10万ドル以上となっています。 (1993年)
データソース:MLA 全農業人口は212,500人で、一戸当り平均人数は1.7人となっています。また平均年齢は46歳で、週あたり平均労働時間は50.4時間と鉱業の41.7時間、製造業の39.7時間を大幅に上回っています。 さらに家族経営の割合は約86%で、企業経営は少なくなっています。 3.
肉牛が乳牛より断然多い
周知のように、日本ではホルスタインなど乳用種の去勢牛を肥育し、肉用として大いに利用しています(全生産の約1/3にあたる)が、このような乳用種の肥育は日本特有の肥育方法と言え、オーストラリア・米国(五大湖沿岸州を除く)では極めて稀なことなのです。 この主な理由は、乳用種は肉用種に対し肥育効率(増体重)が低い為です。従いオーストラリアでも肉用牛(beef cattle)と乳用牛(dairy cattle)の飼養頭数割合は下のグラフの通り、肉用牛が圧倒的です。
データソース:MLA 約60年前の1943年には、牛の総飼養頭数は現在の約3分の1でしたが、それでも乳用牛頭数は多く全体の36%を占めていました。牛の総頭数が約3倍になった現在では、反面乳用種は半減し割合でも9%に減少しています。肉牛がいかに輸出に貢献しているかの証左といえましょう。 乳用牛はオーストラリアの人口(約2,100万人)が少ないことを反映して全体の約9%にあたる3百万頭弱にしかすぎません。フリージャン種の雄牛の利用は日本とは違い主にヴィールveal(子牛肉)として使用するのが一般的ですが、ビーフ全体の消費量の中では大した比率にはなりません。 なお日本の牛の飼養頭数は2002年現在、肉用牛約284万頭、乳用牛約173万頭の合計457万頭ですから、乳用牛の比率は約40%となります。人口がオーストラリアの約6倍で、国内の乳業を手厚く保護している日本は、それだけ乳用牛が多いということになります。 地域的には比較的雨量の多いグレート・ディバイディング・レインジの東側の大都市に近い地域、及びマレー川流域以南が主な乳牛の飼養地域で、州別ではビクトリア州約60%、ニューサウスウェールズ州約15%とこれら2州で全体の約7割を占める南部強勢となっています。したがいヴィール(子牛肉)生産量もこの2州が大半を占めています。 ホルスタイン種は英国肉用種より脂肪交雑(霜降り、サシ、マーブリング)が入るとして、1994年頃から日本向けに日系企業を含む一部の業者が穀物肥育を始めましたが、今後も継続するかは極めて疑問です。 参考 オーストラリアの牛飼養頭数の世界に占める位置 オーストラリアの牛の飼養頭数は、世界の中では上から数えて大体7位の所にあり、世界では決して牛の数の多い国ではありません。インド・ブラジル・中国・アメリカ合衆国・EUが上位5位を占め、これにアルゼンチン・オーストラリア・コロンビア等が続きます。 主要国の牛の飼養頭数と枝肉生産量 (2005年)
データソース:ABARE/USDA ここで注意しなければならないのは、表中のインド、ブラジル、中国、ロシアなどの国は所謂「口蹄疫汚染国」であることです。口蹄疫とは英語でfoot
and mouth diseaseといい、動物の偶蹄目(artiodactyla, cloven-hoofed)のみが発病する家畜伝染病です。家畜の偶蹄目には、奇蹄目(perissodactyl, solid-hoofed)である馬を除く、豚・牛・羊が該当し、その伝播力はすさまじいものがあります。したがいこれらの国から口蹄疫の非汚染国である日本(一度汚染国になりましたが、その後非汚染国に復帰)への生肉の輸出は現実的に不可となっています。 1997年台湾で口蹄疫が発生し、豚肉の輸入全面禁止となったことは記憶に新しい事件です。(但し一定の基準で煮沸処理され、これを日本の農水省が認可すれば可能。) またインド・中国では宗教上・経済上の理由から牛の商業的肥育は未発達で、人口が非常に多いにもかかわらず食用としての貢献度は極めて低いのです。従い人口の少ないオーストラリアは実質的に世界最大の牛肉輸出国の立場を築いています。 したがって枝肉生産量から見てみると、インドは上に述べた理由で第8位となっています。 注目すべきは、アメリカとEU連合です。これらの国は飼養頭数ではそれぞれ第4位、第5位であるにもかかわらず、枝肉生産量では第1位、第3位となっています。これは先進国として飼料穀物が豊富であり、家畜の付加価値化=穀物肥育が進んでおり、一頭当たりの枝肉重量が大きいためであると考えられます。また使役用ではなく食肉用として利用するため、弱齢大型肥育による家畜の回転率が非常に高いためでもあります。(1時点における飼養頭数は少ない。) 南米のアルゼンチンとウルグアイに関しては1995ー1997年相次いで口蹄疫の非汚染が確認され、ヨーロッパ、米国に輸出されるようになりました。これら南米産の競争商品分野としてはとりあえず加工用原料肉が主なもので、米国及び東ヨーロッパでこれらの国と競合しています。 これらの国の牛肉生産コストはオーストラリアに比べはるかに安いため、オーストラリアとしては新たな競争相手の出現に緊張していましたが、2007年ブラジル資本によるAMH、Tasmanの買収は、別の形での競争を挑むものとして、オーストラリアの畜産業界をおおいに震撼させました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||