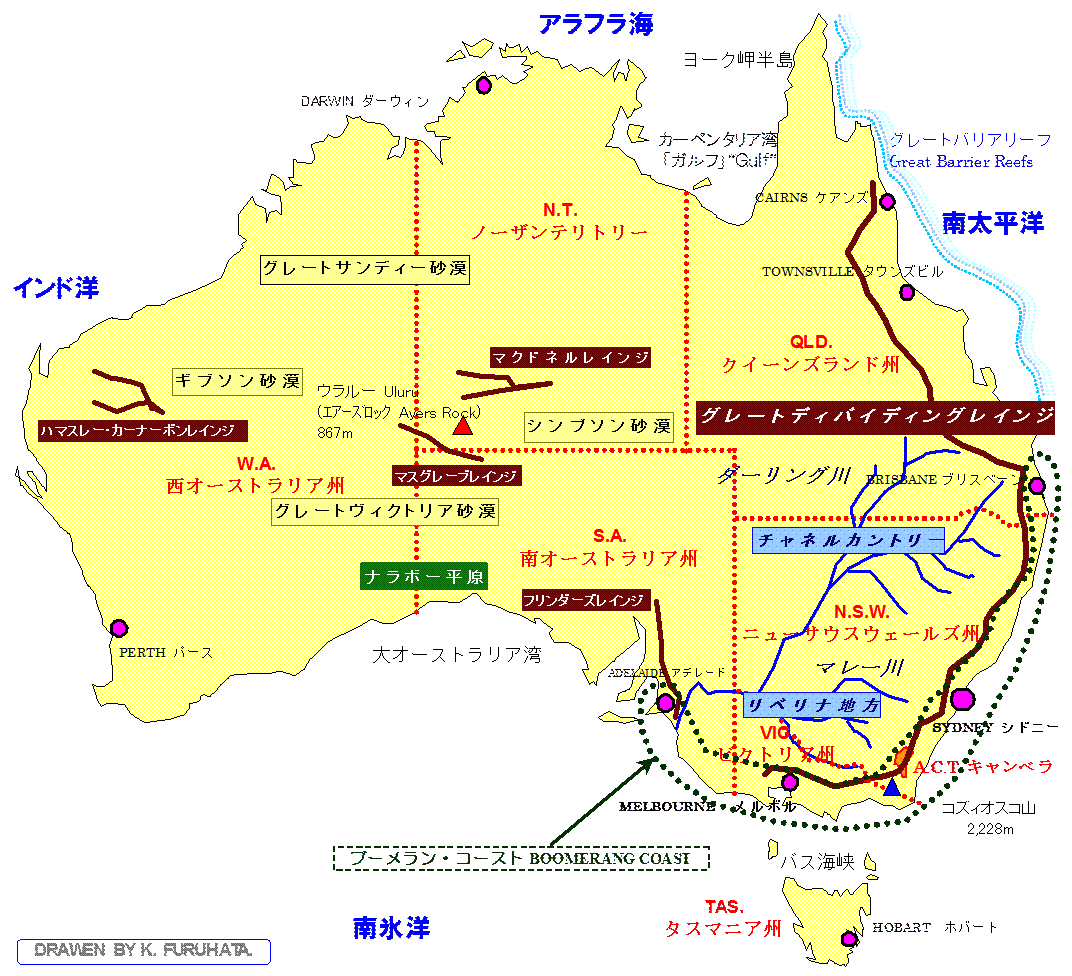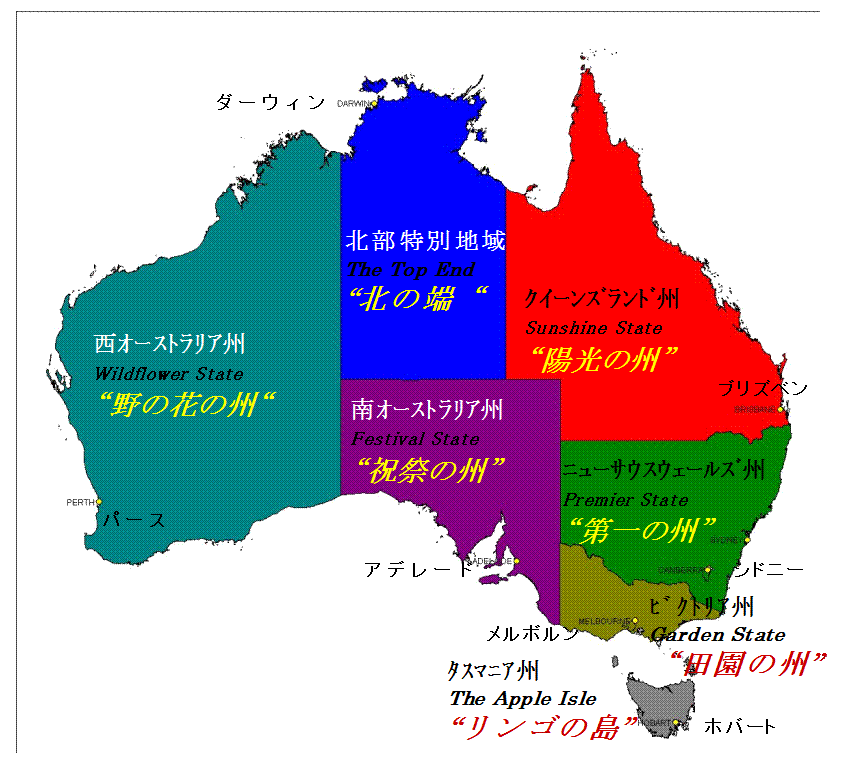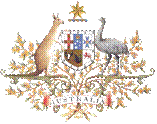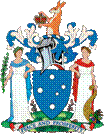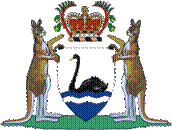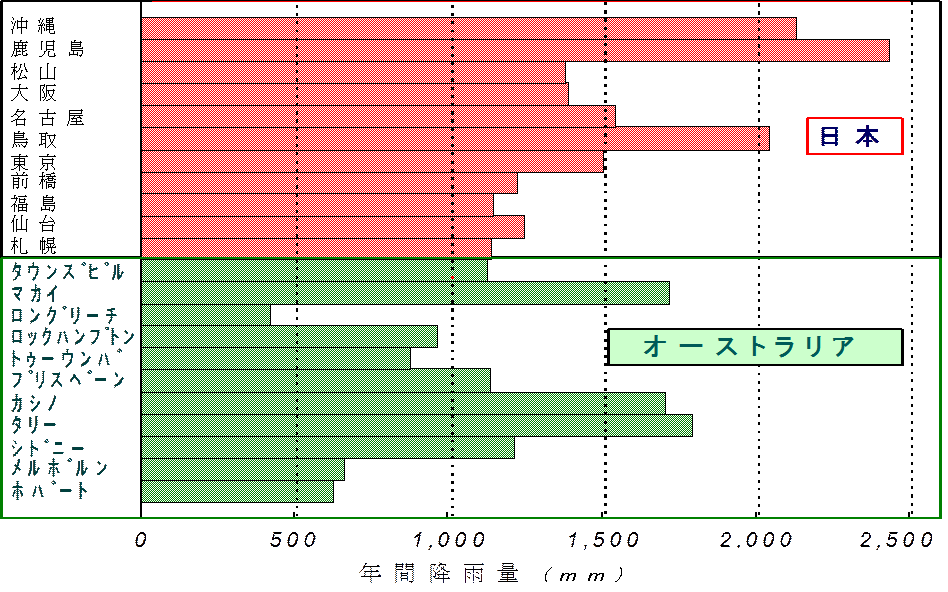1. 広く平たく、他の国から離れている ことがオーストラリアの特徴
まず始めにオーストラリアの地理について、その特徴を簡単に述べます。 このことが、これから述べてゆくオーストラリアの牛肉産業を含む畜産業全体と、そこに生きるオーストラリア人を理解する上でとても重要だからです。 位置 オーストラリアの最大の特徴で、またその畜産業の最大の長所でもあるのですが、オーストラリアは南半球に位置しており、その周りを南太平洋、インド洋、南氷洋など大洋で囲まれた世界最大の「島大陸」なのです。この地理上の「隔離」の意味は大きく、畜産業最大の敵である口蹄疫(Foot & Mouth Disease)、近年人間にも大きな被害をもたらすBSE(牛海綿状脳症:Bovine Spongiform Encephalopathy)、こうした病気を地球上の位置から最も効率的にブロックしているのがオーストラリア大陸なのです。 面積 771.3万km2で日本の約20倍。これはアラスカ等を除いたアメリカ合衆国の本土とほぼ同じ面積です。 アメリカとの比較で大きく違うのは、国土の約70%が砂漠・乾燥した草原など、降雨量が十分でなく、農地として利用できない土地であることです。集約的な産業は、そのほとんどが比較的降雨に恵まれた大陸の東西端の海岸線に沿って立地しています。 その様子は中身が空で、まるで「ピーマン」のようだ、といったら言い過ぎでしょうか。 標高 全土の平均高度が約300mと、世界で最も高度の低い大陸で(世界の平均は約700m)、起伏に乏しく非常に偏平な大陸です。 唯一の大きな山脈といえるグレート・ディバイディング・レインジThe Great
Dividing Range(大分水嶺)は、北はヨーク岬半島基部のケアンズから、南はメルボルンに至る東海岸に沿った全長約2,500kmにも及ぶ長大な山地です。標高は低いところで数百メートル、最も高いところでニューサウスウェールズ州南端のコズィオスコ山Mt. Kosciusko(この一帯はスノーウィ・マウンテンSnowy
Mountainsと呼ばれます)の2,228mです。降雨量が少ない為、そのほとんどは高原状になっています。ただ火山はなく、極めて安定した古い地層から成っています。このため地震はほとんどありません。 なおオーストラリア人は、この長大な山地のことをただ単に「レインジRange」と呼んでいます。 河川 最大の川は、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の州境の流れを本流とするマレー川Murray Riverですが、その支流ダーリング川Darling Riverは本流より長く、なんとオーストラリア最北のクイーンズランド州まで及んでいます。 この川は同州のグレート・ディバイディング・レインジの北部から西の乾燥した内陸奥地に向かって流れ、それから南下してニューサウスウェールズ州を縦断し、ビクトリア州の北部でマレーの本流に合流し、南オーストラリア州のアデレード近くの南氷洋に流入しています。 ダーリング・ダウンズDarling Downsという地名にもなっているこの川は、探検家で発見者のダーリング大佐の名にちなんでいます。 オーストラリアでは年間を通じ常に水のある川は数が少なく、これらはリバーriverと呼ばれます。これに対し雨季のみ水の流れる小河川のことをクリークcreekと呼びます。 乾季にはcreekの河床の所々に水たまり(billabongビラボン)が残りますが、干ばつ時にはbillabongさえ干上がってしまいます。 ちなみにオーストラリアの有名な国民的唱歌である「ワルツィング・マチルダWaltzing Matilda」の中の主人公は、羊盗人の嫌疑をかけられ、悲憤の余りに身を投げてしまうのがこのbillabongです。 なおブリズベン川など大分水嶺から東に向かい太平洋に流れ込む河川は当然ながら短いのです。 気候 オーストラリアは南半球にある為、日本とは逆に北が暑く南が寒いのです。北はヨーク岬半島およびノーザンテリトリー北部の熱帯から、南はタスマニア島の比較的冷涼な温帯までをカバーしています。 このため年間を通じ種々の農作物、特に果物が豊富です。牛の品種の多さも同様で、熱帯牛から英国種までかなり幅広い畜種を擁しています。この約15年間は米国経由で輸入された和牛(F1,F2)も増えて来ています。これについては後述します。 しかし最も特筆すべきことは、降雨量の少なさにあります。このことは次の項で詳しく述べてゆきましょう。 人口 約2,100万人。うち約8割が東海岸のブリズベンから南のアデレードに至るブーメラン状の海岸、いわゆる「ブーメラン・コーストBoomerang Coast」に住んでいます。この比較的人口が密集した都市部に対して、奥地の人口が少ない広大な地域のことをブッシュbushまたはアウトバックoutbackと呼んでいます。 逆説的にではなく、この人口の少ないブッシュこそがオーストラリアの産業を背後から支え、またオーストラリア人の心の故郷となっているのです。 州名 最後に、この本をスムーズに読むために8つの州名とその短縮形を掲載しておきます。 オーストラリアは6つの州と2つの特別地域で構成されています。この本でもこれら8つの行政区域の名前が頻繁に出てきます。また図表・グラフでは、紙面の都合でこれらの州の短縮名も多用しています。各州の名前と短縮名は以下の通りです。 またグラフなどでの州別をわかり易くするため、以下のように州別に色分けを行いましたが、それぞれの色の特定には特に意味はありません。
*
注:日本との時差は、現地でのサマータイム daylight saving を考慮していない。サマータイムの実施と開始・終了時期は州によってまちまちだからである。 各州の概要 各州の位置と愛称、概要は以下の通りです。まず始めにこの地図でそれぞれの州の位置と特徴をイメージしてください。各州の愛称はそれぞれ以下の特徴を表現しています。 · ニューサウスウェールズ州は、オーストラリアの政治経済の中心 ·
ビクトリア州は、比較的安定した年間雨量をベースとした集約的農業 · クイーンズランド州は、亜熱帯をカバーした明るさ · 西オーストラリア州は、乾燥した広大な州 · 南オーストラリア州は、独特の文化とワイン祭り · タスマニア州は、州の形が特産のリンゴに似ている · ノーザンテリトリーは、正式な州でないためか何かそっけない なお赤丸はそれぞれの州都です。
各州の面積と人口、GNPは以下の通りです。 注意すべきは、ビクトリア州が小さいながらも他州より人口、GNPが多いように見えますが、むしろ他州こそが面積が広く人口密度が非常に低いことです。またタスマニアもひとつの州で、反面広大なノーザンテリトリーは準州であることです。従って州旗も他と違っています。 エンブレムには、オーストラリア独自の野生動物である、カンガルー、エミュー、今は絶滅したタスマニアン・タイガーなどが見えます。とくにクイーンズランド州の州章には、牛と羊が自然に守られるように象られていることに着目してください。
注:*-1 2008年3月末現在、*-2
2007年会計年度 畜産州クイーンズランド州のエンブレム(州章)の拡大 2. 雨量が少ないことの意味とは?
オーストラリアは「乾いた島大陸」である
この言葉は、畜産を含むオーストラリアの全農業の成立ちを的確に言い得ていると思われます。オーストラリア全土の年間降雨量は日本の約1/4で、図のように大部分の地域は年間降水量が500mmにも満たない乾燥した土地です。 これに対し、オーストラリアの中では最も雨の多い年間1,000mm以上の地域はおおむね次の3つに区分できます。 a)
降雨地域の分類
北部熱帯・亜熱帯区域 年間総雨量は1,500mm前後と多いのですが、11月−4月の夏期集中豪雨型で、5月−10月の冬期は極端な乾季となる為、サトウキビなど一部を除く一般の農作物栽培には適しません。サイクロン来襲時には、1週間で年間雨量の1/3にあたる500mm以上もの降雨量を記録することがあります。 この地域には気候柄、高湿度・高温に強く、ダニ
tick に対する耐性があるコブ牛系(Zebu種、ゼブ牛)が多いのです。そのほとんどは米国で作出されたブラマン(Brahman)種を原形とする系統で、この畜種は今も飼養頭数が増えています。 またオーストラリアでは一般的に単にバッファローと呼ばれる牛種は、実は水牛water buffaloのことです。北部熱帯・亜熱帯区域の特産となっており、ティーズ社Teys Brosの季節稼動の水牛処理工場もあります。なお水牛は通常の乳肉用の牛とは遺伝子が異なり、これらの「牛」との交配雑種は不可能です。 山脈東側区域 南太平洋に面し、グレート・ディバイディング・レインジの東側に当たるこの区域では年間総雨量は決して多くはありませんが、年間を通じ降雨量が比較的一定しています。 この区域の北半分はどちらかといえば夏期多雨型で、南部(シドニー以南)は夏期・冬期均衡型となっています。 この地域周辺がオーストラリアの牛肉の主産地です。牛の品種は全域にヘレフォードHereford、ショートホーンShorthorn等の英国種系が多いのですが、区域の北部はコブ牛系、中部は皮下脂肪が薄く歩留りの高いヨーロピアン系、南部には一部の日本人に評価の高い英国種系のブラックアンガスBlack Angus、オーストラリア作出種であるマレーグレーMurray Greyの飼養が特徴的です。 南氷洋臨海区域 山脈東側区域と似て年間を通じ降雨量が比較的一定していますが、違う点は冬期多雨型であることです。特にパース近くの西海岸にその傾向が著しくなっています。オーストラリアの冬期とは5月-10月ですから、南半球とはいえ年間降雨量のグラフの曲線の形は日本とほぼ同じです。牛種については上の区域とほぼ同じです。 b)
雨が少ないことは何を意味するか?
ところで、もしもオーストラリアの降雨量が米国並みであったなら、地下資源にも恵まれ、経済民主主義の発達したオーストラリアは世界でも5つの指に入る大国になっていたことは間違いないでしょう。 しかしここでこの事実を逆から考えてみましょう。つまり雨量が少ないということは、実は家畜の伝染病の発生・拡大が最小限に抑えられていることなのではないでしょうか。これは清浄を第一義とした食肉輸出国としての最適の条件でもあることに注目すべきです。オーストラリアではこの清浄な国のイメージをクリーン・アンド・グリーン(clean and green)と標語化し、内外にアピールしています。 さらに皮肉なことなのですが、降水量が少ないことは、穀物・野菜栽培など他の産業を成り立ちにくくし、結果的に低コストでの牛の粗放を保証する(特にクイーンズランド州及びニューサウスウェールズ州内陸部)ため、これも結果的には輸出に大いに貢献していると考えることができます。 ところでオーストラリアでは南部の山岳地帯を除き、積雪はきわめて稀です。ちなみにシドニーから車で約6時間のスノーウィー・マウンテンSnowy Mountainsには冬の間約1ヶ月滑れるスキー場があります。北半球とは季節が逆になる為、最近は、はるばる日本からもスキー客が訪れています。 c)
日本との比較
タスマニアと北海道、シドニーと東京、タリーと鹿児島は、それぞれ緯度的にはほぼ南北逆の位置になっていることが分かます。とくにタスマニアについては地形・気候さらに酪農など産業が似ているため、北海道出身の人がことさら親近感を抱くようです。
またオーストラリアそのものが単一の大陸で、海洋によって他国から隔絶していること。つまり「島大陸」であることも、家畜を含む農業生産物の防疫上、極めて大きな役割を果たしていることは言うまでもありません。 1994ー1996年、引き続く旱魃の影響とフィードロット規模の拡大から海外からの生穀物の輸入の必要性が叫ばれました。これに対し国内の穀物生産業者は外来の害虫・疫病の進入の危険があるとして、搬入フィードロットでの実力阻止を含む反対を行なったことは、このオーストラリアの地理的優位性を明確に表す一例です。 国外からの家畜などの伝染病に対する防疫体制でも、空港・港湾における薬液のスプレー散布はあまりにも有名です。余談ですが、10年ほど前迄は肩章を付けたAQIS(動物検疫所)の係官が到着直後の航空機の中で、乗客を長時間待たせたまま行っていました。最近は航空会社のスタッフが代行するようになり、乗客をあまり待たせなくなりました。 また東南アジアに近いノーザンテリトリーやクイーンズランド州北部ではオーストラリア検疫検査局AQIS (Australian Quarantine Inspection Service)が“AUSVETPLAN”と称する災害時リスクの国側全面負担の防疫システムを確立しています。 これは余り知られていない事実ですが、オーストラリアは毎年年末になると、クリスマス需要のランプステーキ用の牛肉が不足する為、ニュージーランドから輸入をしています。 ニュージーランドもまた島国であり、完璧な防疫体制が確立している為、オーストラリアにとっては数少ない安心できる輸入先なのです。なおオーストラリアから一度日本に輸出してしまった牛肉は、再びオーストラリアに戻すことは、ペットフード用以外にほとんど不可能です。現実にオーストラリアにとって、日本は検疫上清浄性に関して疑問視される国のひとつだからです。 また最近では、米国からも少量ですが牛肉が輸入されています。これについては国民の一部から感情的な反発があるようです。 3. かんばつとは? 畜産に及ぼす影響
有史以来オーストラリアの農畜産業の歴史は、旱魃droughtとの戦いの歴史であったと言っても過言ではありません。 雨量に恵まれ、水利の発達した日本からは想像し難いのですが、それは過酷な自然、特に絶対的な降雨量の不足との戦いの歴史でした。 つまり作物の播種・発芽がうまくゆくかどうかはほとんどの場合降雨次第ですし、旱魃時期には牛を競って市場に出さなければ相場の暴落のあおりを受けてしまいます。また暴落がいつ回復に向かうかもお天気次第で、牛を自分の牧場にホールドするのも賭けのようなもので、予測というには程遠いのです。最近ではエルニーニョとの関連が研究され、ある程度の予測が可能となったとはいえ、こうした大いなる自然に抗っても仕方がない連綿とした歴史の中で、有名なオーストラリア英語の”No
Worry, Mate.”(心配要らんよ、あんた。)が生まれて来たと筆者は想像するのです。 旱魃の地域的な特定はその年毎にされる程度で、次表のように旱魃がいままで来たことがないというような地域はありません。つまりどの地域でも旱魃になりうるのであり、たとえば1992〜1994年にビクトリア州が旱魃の害からほぼ免れたことは同州の農畜産業界にとり非常にラッキーだったといわねばなりません。経済に深刻な影響を与えた大きな干ばつは過去180年間に8回起きており、大体18年に1回の割合だそうです。
豪州気象局 ところで旱魃がひどくなると、繁殖業者は最低限の再生産ライン(繁殖用メス牛)を守る為、生産能力が乏しく肉の価格も低い高月齢(畜産業界では「年齢」とは言わない)のメス牛(dry cow)や妊娠能力に乏しい若齢メス(cull heifers, cull
cows)から順番に家畜市場・パッカーに出荷してゆくことになります。それでも旱魃が治まらなければ、再生産能力のあるメス牛をも淘汰(cull)しなければならなくなるのです。 オーストラリアのメス牛の淘汰比率は通常38%前後が常態とされていますが、この数字が40%を超えると全体の飼養頭数が1〜2年後減ってゆくのです。ちなみに旱魃がオーストラリアよりはるかに少ない米国のメス牛淘汰率は約50%となっています。 肥育業者の商品は主に去勢牛ですから、肥育業者は旱魃が来ると、より増体重の少なく、価格の安い所謂「ガリ牛」から出荷することになるのです。なお1日当たりの増体重のことを、専門用語でデイリー・ゲインdaily gainといい、通常の牧草肥育の去勢牛は1.5から2kgsのデイリー・ゲインです。 ところでオーストラリアには米国・日本の通常の辞書には載っていない、アジストメント(agistment)という単語があります。これは、旱魃で自分の牧場の草が全て枯れ果て牛群(cattle herd)が維持できなくなったとき、牛群を他人の地所に移動し、牧草代金を払って牛群の維持に努めることを言います。この言葉はもともと英国からきたと思われますが、今ではオーストラリアのみに生きている単語でしょう。勿論こうした状況下では公有地の道路脇の草も利用します。 しかし1990年頃からは第一次産業省などの政府機関の努力が功を奏しています。繁殖技術の向上や有効な補助飼料(supplement サプリメント)の普及もあり、旱魃の影響による牛群の減少率はかなり低くなりました。 100年に一度といわれる2006年の干ばつは、前回2002/03年の干ばつと比較して、主要肉牛生産地域であるQLD州での被害規模が小さいことや、肉牛生産農家での干ばつ対策が整っていたといわれます。従い、早急に牛群の再構築が行われ、肉牛飼養頭数の回復も早いとの見方も一般的です。 しかし干ばつの被害が少ないQLD州北部では、アメリカ向けの熱帯種が多く、反面干ばつ被害の多いQLD州南部からNSW州、VIC州では日本向けの穀物肥育用としてのアンガス、ヘレフォードなど英国種が多いことは日本向け輸出にやや影響が出ると思われます。なお今回は西オーストラリア州や南オーストラリア州では干ばつの被害は大きくありませんでした。 なおブッシュbush(田舎、奥地)に居住し学校まで距離がかなりある場合、農業従事者などは子女を町のボーダー・スクールborder schoolと呼ばれる全寮制の学校に入れるのが一般的です。ところが旱魃が長期化して収入が無くなり学費の支払いに困ると、子供を学校から引き上げて自宅に帰してしまうことも現実に起きています。長期の旱魃は教育問題にまで深刻な影響を及ぼすので、これを防止する為に旱魃時教育費補助金制度があります。 また総合的農業政策(AAA:Agriculture
Advancing Australia)の一環として、EC (例外的環境Exceptional Circumstances)=かなり深刻な状況であると認定された場合には、ケースによって違いますが、認定者には再出発手当てNewstart Allowanceとして2週間当たり最高約400ドル前後が支給され、配偶者手当Partner Allowanceとして2週間当たり350ドル、無料診察保険カードHealth Care Cardの支給などもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||